※本記事は、『アニメルカ vol. 2』(アニメルカ製作委員会、2010)所収の志津A「日常における遠景──「エンドレスエイト」で『けいおん!』を読む」を一部加筆・再構成のうえ、転載したものです。
文:志津史比古
夏の雲、冷たい雨、秋の風の匂い、傘に当たる雨の音、春の土の柔らかさ、夜中のコンビニの安心する感じ、放課後のひんやりとした空気、黒板消しの匂い、夜中のトラックの遠い音、夕立のアスファルトの匂い。
新海誠の『ほしのこえ』(2002)で、ノボルとミカコは、日常生活に見出される価値あるもの(「いま・ここ」に生きている実感を凝縮して示している小さな断片)をこんなふうに列挙していく。(『ほしのこえ』がそうであるような)「セカイ系」では、非日常的な状況(「いま・ここ」とは対照的な、時間的・空間的に遠く隔たっているという観念)を持ち出すことで、日常の価値を逆照射しているところがあった。こうした日常の価値を、非日常的な設定を持ち出すことなく、率直に称揚していく作品が「日常系」なのではないか。
もしこのようにセカイ系と日常系との間に繫がりを見出せるならば、日常系のうちにセカイ系の要素を見出すのも可能ではないだろうか。言い換えれば、日常系においても、ただ単に平板な風景だけが提示されているのではなく、何らかの奥行きを見出すことができるのではないだろうか。

『思想地図』第4号に収録されている座談会「物語とアニメーションの未来」において、日常系の代表作とも言える『けいおん!』(2009)は、ただ単に「近景のみ」を描いた作品として、批判的に捉えられていた。その前段では、アニメにおける奇跡の描写が話題となり(奇跡とは不可能なことが起こるという意味だろう)、セカイ系がそれを描けていたのは、そこに「不可能なものへの志向」や「遠いものに対する執着」があったからだとされる。これがセカイ系の方向であるとしたら、「ポストセカイ系としての『けいおん!』」には「近景」しか見出されないというのだ1。
この座談会で具体的にセカイ系として名前が挙がっているのは、『AIR』(2005)と『CLANNAD』(2007−08)である。この2作品は、『けいおん!』と同様に、京都アニメーションによって制作されたアニメだ、という点に注目すべきだろう。つまり、ここで語られている事柄を京都アニメーションの作品傾向の変遷の問題として考えるならば、Keyブランドの美少女ゲーム(ノベルゲーム)を原作にしたアニメと『けいおん!』との間には大きな断絶線が走っていることになる。
しかし、そうなのだろうか。『けいおん!』を『AIR』や『CLANNAD』に近い作品として考えることはできないのだろうか。『けいおん!』では本当に奇跡が描かれていないのだろうか。京都アニメーションの作品傾向のうちに何らかの変化が認められるとしても、それをもっと別の仕方で位置づけることはできないのだろうか。
京都アニメーションにおいて、セカイ系と日常系との接続が目指されているとすれば、あるいは、セカイ系とか日常系といったレッテルとは別のところで何かが模索されているとすれば、Key原作のアニメと『けいおん!』を比べるだけでなく、『涼宮ハルヒの憂鬱』(2006)や『らき☆すた』(2007)にも注目すべきだろう。これらの作品でセカイ系的な要素がどのように取り扱われているのかという点に注目することで、『けいおん!』の風景に奥行きを見出せるように思うのだ。とりわけ「エンドレスエイト」を日常系のパロディと捉えることによって、『けいおん!』の戦略性を際立たせられるのではないか。これが〈「エンドレスエイト」で『けいおん!』を読む〉ということである。
日常の彼方としての遠景
アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』は2009年に、新しいエピソードが追加されて、第2期として改めて放送された。その新エピソードのひとつが「エンドレスエイト」である。
このエピソードが描き出しているのは、夏休み最後の2週間が1万5000回以上も繰り返されるという異常な事態だ。原作小説ではそのうちの最後の1回のみが描かれていたのに対して、アニメではその中から8回を抜き出し、それぞれの回を映像化した、という体裁になっている。つまり、ほとんど同じ話が連続して8回も放送されたという点で物議を醸した(もっと言えば悪評を買った)エピソードなのである。

そもそも『ハルヒ』では何が描かれていたのだろうか。この作品の主題を簡単に要約すると、日常からの遊離といった傾向性──それをセカイ系と呼んでもいいだろう──をいかにして引き戻すことができるか、あるいは、この世界に現に生きているという事実を、あらゆる仮想や仮定に抗して、いかにして肯定することができるか、というものであるように思える。涼宮ハルヒというキャラクターには、世界の成立条件そのものを変更する能力が与えられている。つまり彼女が望めば、ここではないどこかへといつでも旅立つことができる。そうした変更可能性があるにもかかわらず、各エピソードにおいて、主要キャラクターたちはいつも自分たちの存在している「この世界」を選び直す。この世界からいったん距離を取り、再び戻ってくるというその振幅が、『ハルヒ』において、日常生活を再び価値づけることになっているのだ。
これに対して、日常系はもっと直接的な仕方で日常の価値づけを行う。日常生活の決まり切ったルーチンワークにあっては見過ごされていたもの、低く見積もられていたものに新鮮な価値を付与するというのがそれである。「この街って奇跡で出来てるんだよね」という『ARIA』(2005年から2008年にかけて3期にわたってテレビアニメが放送された)の台詞が典型的であるが、普段見慣れた当たり前のものを奇跡的な出来事の産物と見なすという、そのまなざしが日常生活に再び価値を付与することになる。
この観点からすると、『ハルヒ』も『けいおん!』も、同種の事態を描き出していると言える。世界の終わりといった極限状況を背景にして絶対不変の基盤(きみとぼくとの合一)を探求することが奨励されないのはもちろんのこと、後に見るように、日常生活における具体的な人間関係の親密なコミュニケーションへの埋没も是とされない。そこで目指されているのは、言ってみれば、日常から緩やかに飛翔し、再び日常に緩やかに着地するという軽さなのだ。こうした軽やかさを(とりわけ風景という形で)描き出すのが、この時期の京都アニメーションの方向性だったと言っていいだろう。
『ハルヒ』も『けいおん!』も以上のようなバランス感覚の下で見事に成立していた作品であり、そうした意味で、『けいおん!』をいつまでも続く日常生活の戯れを描いた作品として、つまりは単に近景のみを描いた作品として捉えることには、大きな見逃しがあるように思うのである。
「エンドレスエイト」には、単純に、楽しい夏休みが終わってしまうことに対する不安が示されていると言える。いつまでもこの楽しい日々が続いてほしい。だが、実際に夏休みが終わらなかったらどうなるだろうか。このエピソードが見事に印づけているのは、楽しいはずの夏休みのイベントが悪夢へと変わるという、逆転の瞬間である2。
夏休みがいつまでも続いてほしいというのは分かりやすい願いであるが、これを楽しい時間への執着として捉えるならば、そこで生じている事態は長期休暇に限定される話ではない。すでに『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984)でも、学園祭の前日が永遠に繰り返されるという事態が描かれていた。ここには、学園祭は当日よりも準備期間のほうが楽しい、という考えが如実に示されている。学園祭当日は楽しい時間の終わりの始まりである。ならば、その到来を引き延ばせば、楽しい時間はいつまでも続く。多くのサブカルチャー作品にとって、学園祭や文化祭が特別なイベントとして位置づけられているのは、このようなニュアンスを含んでいるからであり、さらに言えば、それが(この種の作品群の基本的な雰囲気でもある)親密な共同体における終わらないお祭り騒ぎを象徴しているからである。
学園祭をはじめとした様々な学校行事、さらには(夏は海、冬は雪といった)季節ごとに特有のイベント。こうした毎年繰り返されている出来事を軸に話を展開させる作品は無数に存在する。その意味では、設定やキャラクターの違いはあるとしても、同じような出来事が何度も繰り返し描かれつづけているという意味で、「エンドレスエイト」は現在のサブカルチャーをメタ視点から描き出したエピソードだ、と言うこともできる。こうした観点から考えてみるならば、「エンドレスエイト」で問われているのは、(中学や高校といった学園を舞台にした作品に顕著に見出される)楽しい時間への執着からいったいどのようにして外に出られるのか(それも日常からは完全には遊離しない形で)、ということだったように思えるのである。
この出口への示唆として、「エンドレスエイト」で描かれる興味深い風景がある。それがまさに遠景であると思われるのだが、それは第4回目の「エンドレスエイト」で描かれる風景だ3。この回では積乱雲(入道雲)と模型飛行機が象徴的なイメージとして何度も出てくる。これらのイメージが示しているのは、遠い場所やここではないどこか、といったものだろう。あるいは、「いま・ここ」からの飛翔が示されているとも言える。この回の「エンドレスエイト」では、(主人公の)キョンが何度か積乱雲や飛行機を見上げる場面がある。このとき彼は、決して終わりがやってこない日常の無限地獄の彼方を見つめているかのようだ。

こうした遠景は、セカイ系と呼ばれる作品群に特有の風景だとも言える。分かりやすい例として新海誠の名前を出そう。彼の2004年の作品に『雲のむこう、約束の場所』がある。タイトルが示しているように、彼方は「雲のむこう」にあるものと想定されている。作中でこの彼方は、分割統治された日本の向こう側、北海道に建設された巨大な塔として示される。この塔が遠景としての機能を果たしているのは、それが日常生活の後景に染みのように張りついているからだ。内側にありつつも、向こう側を指し示す指標として機能するもの。これが日常における遠景である。
さらに新海誠と「エンドレスエイト」を近づけてみよう。彼の最初期の短編に『遠い世界』(1999)というものがある。このアニメで描かれているのも、この世界の外にある「遠い世界」なわけだが、そこへの飛翔を示すモチーフとして模型飛行機と鳥が出てくる。模型飛行機や鳥はここではないどこかへと飛んでいくことができる4。しかし、この短編に出てくるカップルはただ地上を這って歩くことしかできない。「飛んで行けぬものならば、足を引き摺ってでも行かねばならぬ」5とでも言うかのように。
「エンドレスエイト」には(あるいはセカイ系の諸作品には)、「いま・ここ」にある日常の出口としての「遠い世界」を見つめつづけるノスタルジックなまなざしが存在する。なぜノスタルジックなのかと言えば、現在自分のいる地点と過去に自分がいたそれとの間の距離が遠さの観念を生み出すからだ(『AIR』において空を見つめる神尾観鈴の台詞「もうひとりの自分がそこにいる」を思い出してほしい)。「エンドレスエイト」では、こうしたノスタルジーとは異なるまなざしも提示されている。それは長門有希のまなざしである。彼女は、他のキャラクターとは異なり、同じ日常が何度も繰り返されていることを観測し、数え上げていた。言い換えれば、彼女は、ほとんど同じような日常のちょっとした差異、つまりその固有性に敏感に反応できる目を持っていたのだ。
「エンドレスエイト」の解決は、まさに、この超越的なまなざしを獲得することによって得られたと言える。日常地獄の出口は、こことは異なる「遠い世界」に実際に行くことによって見出されるのではない。そうではなく、日常生活の最小限の差異に気がつき、確率論的にもたらされた偶然の一回性に自覚的になることによって辿り着ける。この解決は、言うなれば、彼方を見つめつつも日常にとどまるというものであり、ある意味においては、充実した日常生活の終わり(夏休みの終わり)をも引き受ける行為だと言える。これが「エンドレスエイト」の出口である6。
楽しい夏休みがいつまでも続いてほしいという思いが一方にはある。そうだとしても、それが600年近くも続けば、地獄だろう。相反する2つの思いがここにはある。この素晴らしい日々が永遠に続いてほしいが、終わりの来ない日常地獄からは脱出したい。いわゆる日常系が、それぞれの作品において、こうした葛藤にどのような出口を与えているのかに注目すべきである。言い換えれば、日常系において、「いま・ここ」から脱出したいという彼方への欲望が見出されないかどうか(グループ内の息苦しいコミュニケーション関係から脱出したいという欲望が見出されないかどうか)という点を問題にする必要があるように思うのだ。
日常系の裏面としての孤独
日常系のうちに遠景(彼方への視線)を見出すというのは、それらの作品群の裏面を問うことでもある。仲良しグループの充実した日々を描いているだけのように見える日常系の成立条件のうちに、それとは正反対の、孤独の問題が提起されているとすれば、どうだろうか。これは、とりわけアニメ『かなめも』(2009)が取り扱っていた主題である。
『かなめも』は、原作マンガが『まんがタイムきららMAX』に連載されていたという点で、『けいおん!』と同様(『けいおん!』は『まんがタイムきらら』連載)、いわゆる萌え四コマ、日常系四コマのアニメ化だと、ひとまずは言うことができる。しかし、この作品は「日常系萌え四コマ原作」という言葉からイメージされるものとはやや異なった側面を強く打ち出していて、その点で、ネットの一部で物議を醸したアニメだった。
アニメ『かなめも』のどこがそんなに特別だったのか。この点を論じているブログの記事がいくつかある。例えば、『やまなしなひび』の「『けいおん!』は “仲間” を描き、『かなめも』は “孤独” を描いた」では、「『かなめも』は『けいおん!』を裏返した作品」「中町かなは、「平沢唯になれなかった」主人公」といった言い方で、2つのアニメを対立させて論じている7。
ざっくばらんに言ってしまえば、『かなめも』に描かれているのは擬似家族である。唯一の肉親であった祖母の死によって、中学生の中町かなは、天涯孤独の身となる。行き場所を失った彼女は、風新新聞専売所へと辿り着き、そこで住み込みで働く。この専売所は、単に労働の場所としてだけではなく、行き場所を失った者を温かく迎え入れるアジール、あるいは家族の機能を肩代わりする共同体として機能する8。こうした場を舞台として、日常生活の小さな幸せを描く、というのがこの作品の基本的な方向性だと言っていいだろう。

高橋留美子の『めぞん一刻』(1980−87)を代表とする擬似家族のユートピアは、2000年代のサブカルチャーにおいても、様々なヴァリエーションの下で描かれてきた。そうした作品においては、プライバシーの領域にどこまで他人が入りこんでくるかという点で、具体的な間取りがどうなっているかという住宅の構造が重要になってくる。自室の壁に穴が開いていて隣の部屋と繫がっており、夜になると宴会が開かれるという、『めぞん一刻』で描かれたシチュエーションがそのまま再現されているという点で、『かなめも』も典型的な擬似家族作品である。だが、このアニメが注目に値するのはそうしたところではない。
重要なのは、『かなめも』において、そうした擬似家族的な共同生活に対する一種の不安が示されている点である。すなわち、風新新聞専売所がある種の避難所として機能していて、孤独な人間がそこに辿り着けたのは幸運だったとしても、果たしていつまでもここに居つづけられるのだろうか、ここで成立している理想的な人間関係もいつかは破綻するような類いのものではないのか、と。
これと似た不安は、すでに『がくえんゆーとぴあ まなびストレート!』(2007)でも示されていた。「がくえんゆーとぴあ」というタイトルからも理解されるように、このアニメで描かれるのも、学園=ユートピアという充実した日常生活である。
『まなび』の物語は、2段階のプロセスを経て進行する。初めに、退屈で不活性な学園生活が提示される。この不活性さに対する改革者として天宮学美(あまみや・まなみ)という転校生が現れる。彼女が生徒会長になることによって、学園生活が再び活性化する。しかし、そんなふうにユートピアとなった学園にいつまでもとどまりつづけるのは果たして良いことなのか、という疑問が最終回で提示される。作品の結論としては、いつまでも同じ場所にとどまるのは好ましくないこととされ、生徒会のメンバーたちはそれぞれ新しい場所に旅立っていく。簡単に言ってしまうと、ここでは「卒業」が描かれるのだ。
『まなび』の「卒業」は、ある種、倫理的な選択という趣があったが、『かなめも』のそれは、そうした自己決定以前の(外から到来する)不可避の出来事という形を取る。かなは、祖母よりも前に、事故で両親を亡くしている。そんなふうに親しい人たちもいずれはいなくなってしまうとすれば、専売所のみんなとの楽しい生活もいつかは終わりを迎えるだろう、と。つまるところ、かなは、楽しい日常生活の終わりを常に先取りし、現在の充実した風景のうちに終末のそれを重ね合わせて見ているという意味で、メランコリーなのである。
楽しい日常生活の終わりを性急に先取りするというかなの態度は、ある意味において、その到来をどこまでも先延ばしにしようとするサブカルチャー作品の基本的な傾向性に対して疑問を提起しているとも言えるだろう(これは『ビューティフル・ドリーマー』が『うる星やつら』(1978−87)そのものに対して批判的な観点を提示していたのと同様である)。セカイ系においても、終わりに対する過度な意識(メランコリックな意識)を見出すことができるが(例えば高橋しんのマンガ『最終兵器彼女』(2000−01))、それを日常系の内部で真正面から行っている点で、『かなめも』は、かなり特異な作品になっているのである。
アニメ『かなめも』で描かれているのは、二重写しの風景、未来から過去を振り返った回顧的な視点が折り畳まれている風景だと言える。典型的なのは第10話で描かれる誰もいない食卓である。ただ単にみんな外出していてその場に誰もいないだけなのだが、かなにとっては、楽しい日々が終わってしまった(理想的な人間関係が崩壊してしまった)未来の風景のように見えるのだ。

第10話にはまた、みんなが花火をしている背後で、かながひとり、線香花火をじっと見つめている印象的なショットがある。花火は(「エンドレスエイト」や『けいおん!』でも用いられているように)極めて象徴的な道具立てである。ほんの短い間だけ、美しい光を放つ花火。この点で、花火は日常生活の楽しい時間を象徴していると言える。だが、かなは、喪失を先取りするがゆえに、花火の美しさよりも、その消失(線香花火の落下)のほうに気を取られてしまうのだ。
さらにこの第10話では、人間関係が壊れてしまうことに対する、かなの極端なまでの不安が描かれていた。かなは、終わりの到来を恐れるがゆえに、ちょっとした人間関係のいざこざにも過敏になっている。ここで逆説的に示されているのは、日常系の基盤にあるような仲良しグループの閉鎖性、そこにおけるコミュニケーション環境の出口のなさ、といったものである。親密なコミュニケーションが、擬似家族や仲良しグループといった形で、孤独の不安を解消するとしても、同時にそれは、関係性への過度な依存という形で、お互いを縛りつける枷となる。ほのぼの日常系には、そうした人間関係の暗い領域が直接的に描かれることは少ないが、こうした作品を楽しみつつも、孤独と隣り合わせになったコミュニケーションの息苦しさに意識が向かう人がいても、何もおかしくはないだろう9。
では、こうした孤独の問題に対して、『かなめも』は、どのような解決を提示していたのだろうか。『かなめも』において、不安の出口として示されていたのは、アニメのオリジナルキャラクターであるマリモの存在である。彼女は、風新新聞専売所にかつていた人物として、つまり関係性の外に出て行った人物として登場する。マリモもまた風新新聞専売所に自分の居場所を見出し、そこで充実した日々を送っていたわけだが、そんな彼女が共同体の外に出ても、同じような生活が送れているのかどうか(あるいはマリモのいなくなった風新新聞専売所のメンバーは彼女との関係性をどんなふうに維持しつづけているのか)といった点が問題となる。
かなとマリモが偶然出会うエピソード(第12話)が重要である。かなが自分の不安を話した後、マリモは『椰子の実』(島崎藤村作詞)を歌う(「名も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実一つ」)。これは望郷の歌であるが、それに対してマリモは、故郷を離れて漂う椰子の実は旅の途上にあって楽しそうだ、とポジティヴな解釈をほどこす。これは、ある種、『まなび』の解決とほとんど同じなわけだが、人間誰しもが海上を漂う椰子の実のようなもので、同じところにとどまりつづけることは決してないが、そうした旅そのものの中にも多くの楽しみが、とりわけ新しい出会いという楽しみがあるということが示唆されているのである。
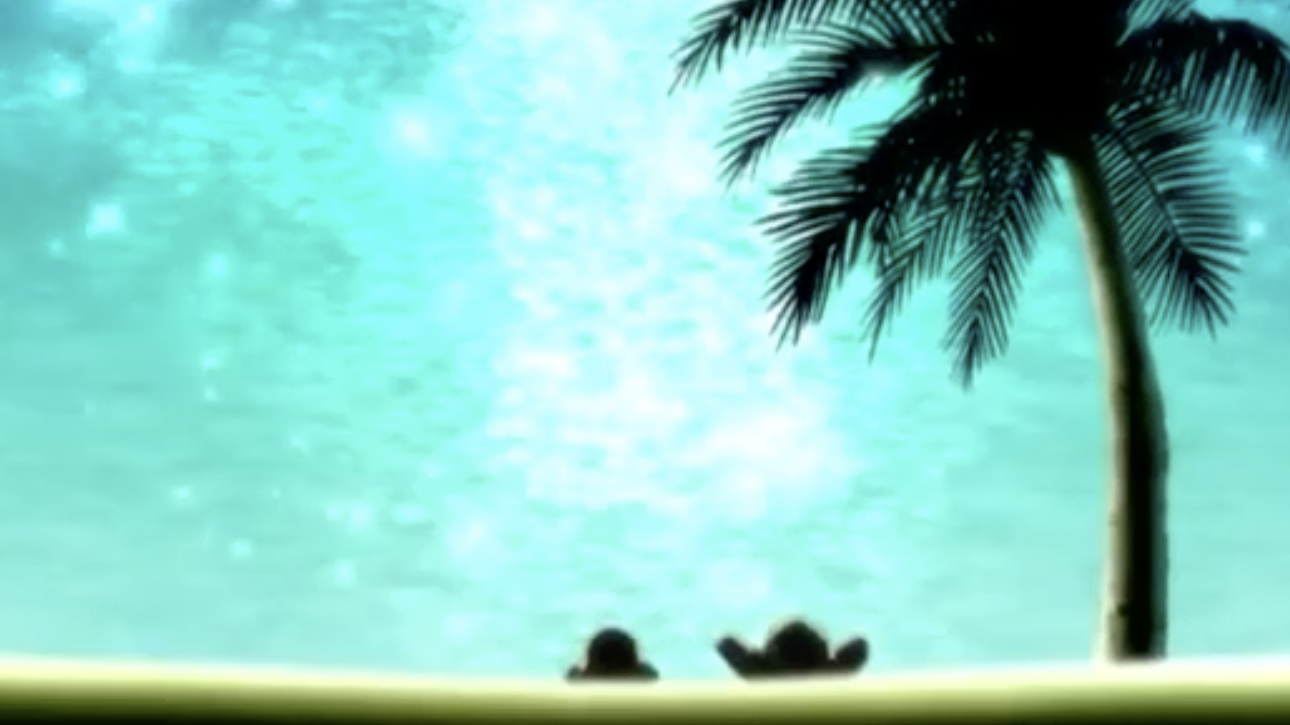
「エンドレスエイト」では日常地獄からの脱出口が探し求められていたわけだが、この探索は、『かなめも』の観点から言えば、コミュニケーション関係から外に出て孤独になる不安と表裏一体のところがある。海上にひとつだけ浮かんで漂う椰子の実を、積乱雲に向かって飛翔する模型飛行機のイメージと重ね合わせることもできるだろう。マリモが『椰子の実』を歌うことによって示したのは、未来の終わった地点から現在を常に過去のものとして眺めるかなの視線を、未知なる未来へと方向転換させることにあったと言える。つまり、彼方へのイメージを出現させることが『かなめも』の出口だったのである。
「いま・ここ」にある彼方
「エンドレスエイト」や『かなめも』で示されていた日常系の暗い領域。それを『けいおん!』にストレートな形で見出すのは困難だ。だが、日常からの出口としての彼方への視線が『けいおん!』にも見出されるとしたら、どうだろうか。つまり、この作品が、ただ単に日常における戯れだけを描いているのではなく、こうした暗い領域を最初から織りこんでいて、それに対する解決を示しているとしたら、どうだろうか。
『けいおん!』に彼方への視線を見出していく作業は、この作品の戦略を推し測っていくことでもある。日常生活を舞台にした闘争(この現実の生を、そこから逃れたいという思いと折り合いをつけながら、いかにして肯定することができるか)を、『けいおん!』は、どのように成し遂げているのだろうか。
『けいおん!』の戦略を見ていく前に『らき☆すた』に一瞥を加えておこう。
『らき☆すた』が典型的な日常系になっているのは、この作品が物語の水準でのまとまりを拒絶しているからである10。もちろん、部分的に切り出すならば、そこに何かしらの物語(思春期の若者に焦点を当てたときに生起されがちな成長の主題など)を見出すことは可能だろう。だが、この作品の魅力は、そうしたところよりもむしろ、話の前後関係が切断され、断片化するところにある。言い換えれば、いかにして意味づけの重みを減らすか、ということが『らき☆すた』の課題になっているように思うのだ。
雑談という会話形式がそうした意味の軽量化の代表例である。もちろん雑談も、仲良しグループ内のコミュニケーション関係(グループ内での立ち位置やキャラづけ)という水準で見るならば、そこでのどんな細かい発話行為にも意味づけを行うことは可能だろう。発言の裏をいろいろと読んで、作品の表には出てこない、キャラクターたちの暗い領域を想像することもできる。だが、そうだとしても、このアニメを見るにあたっては、意味を軽くする戦略が様々な仕方で行われている点にもっと注目すべきである。
その戦略の象徴とも言えるのが、『らき☆すた』第1話に出てくるチョココロネである。チョココロネにまつわる雑談は端的に無意味である。ここでの会話が、『らき☆すた』という物語全体の中で、固有の意味をもって(例えばその後の展開にとって重要な伏線になっているなどといった形で)位置づけられることはない。チョココロネの太いほうと細いほう、どちらから先に食べるべきなのか。あるいは、どちらが頭でどちらが尻尾なのか。そんなふうに、チョココロネを巡ってどうでもいい会話をすることのうちに、世界との戯れという戦略が見出される11。言い換えれば、端的に無意味なものがチョココロネという物質に結晶化されている点に、『らき☆すた』の明確な方向性が見出されるのである12。

しかし、そんなふうに世界と戯れている『らき☆すた』にあっても、日常における遠景が描かれる場面がいくつかある。その代表例が、第22話「ここにある彼方」の最後に示される、主人公こなたの死んだ母(泉かなた)にまつわるエピソードだ。
『らき☆すた』において、母親がすでに死んでいるという不穏な設定がなぜ入りこんでいるのだろうか。この設定から何かしらの物語が生まれてくる余地があるが、それをこのエピソードでは、ギリギリのところで抑えこんでいる。逆に言えば、このエピソードが示しているのは、日常系の無意味な戯れの背後には、物語への志向が潜在している、ということだ。あるいは、物語の終わった地点から日常系が始まっている、とも言えるだろう。
此方(泉こなた)と彼方(泉かなた)との対比が重要である。第22話で亡霊の形で示される母の視線。これは、過去から未来をまなざしている視線(母の願い)だと言える。父と母の、出会いから別れへと至る、走馬灯のようなフラッシュバックのうちに、彼方の風景(夕日に輝く海など)が見出されるわけだが、この過去の物語の出口は、父と娘との平穏な日常のうちに開かれている。つまり、『らき☆すた』の現在がすでにひとつの出口になっているのである。死別に代表されるようなドラマティックな物語展開が起こらないという日常系の特徴は、その否定性のうちに彼方へのまなざしを宿していると言える。こうした潜在したまなざしこそが「ここにある彼方」であるだろう。

同種のまなざしが『けいおん!』にも見出されることをこれから示してみたい。
『けいおん!』が日常生活の充実を描いているのは間違いない。このアニメがバンドものだということから、成長物語が描かれるのを期待した人もいるかもしれないが、『けいおん!』は、それをはぐらかすかのように、実演や練習よりも、部室でまったり過ごす時間(放課後ティータイム)を描き出すほうに力を入れている13。こんなふうに、のんびりと時間を過ごすことの重要性を示し、仲良しグループの日々の戯れを描いているという点で、『けいおん!』は、間違いなく、日常系の代表的な作品である。
だが、アニメの『けいおん!』には、それだけでなく、充実した日々を遠くから眺める視点が随所に潜在している。軽音部の日常は非常に輝かしいものであるわけだが、そこにかけがえのない美しさを見出している視点が存在するのだ。
(主人公の)唯はなぜ軽音部に入ったのだろうか。第1話の『翼をください』の演奏シーンには『けいおん!』のエッセンスが凝縮されている。これは彼方への飛翔をこいねがう歌と言えるが(「この大空に翼をひろげ飛んで行きたいよ」)、その崇高なイメージに反して、軽音部の演奏は小さな部屋の中で控えめに鳴り響いているだけだ。つまり、日常生活の出口が実際にどこかに開かれるわけではない。しかし、そこには、暖かい午後の日差しがある。日差しという形で、この日常それ自体のうちに輝きが見出せることを遠くから再発見しているまなざしが示されているのだ14。

唯もまたこの輝きを見出したがゆえに、軽音部に入ったと考えるべきだろう。彼女は初め、カスタネットの演奏なら自分にもできるかもしれないと思って、軽音部にやってきた。この時点では、自分にできることは何かということを考えて、部活選びをしていたと言える。唯は澪たちの演奏を聞いたあとに軽音部に入るのを決めたわけだが、それは、彼女たち程度の演奏ならば自分にもできると思ったからではもちろんないだろう。唯が実感したのは、演奏の上手い下手とは別の水準で、この日常に輝きをもたらすことが音楽には可能だ、といったことではないだろうか。「あんまりうまくないですね」という唯の感想にはそうしたニュアンスが込められているように思える。
唯が澪たちの演奏を聞いて感得したことを、今度は逆に、澪が唯の振る舞いを見て実感するシーンがある。それは第4話、1年生のときの合宿で、花火をバックに唯がプロミュージシャンの真似事をするシーンである。花火のもたらす一瞬の輝きが、澪に軽音部の本質を再発見させる。それは、成功しメジャーになった軽音部の未来の姿といった即物的なものではない。「いま・ここ」での演奏活動それ自体のうちに輝きが見出せるのである。このとき、澪は、おそらく彼女が楽器を始めた動機をも思い出したのではないだろうか(同種の輝きを梓もまた見出して、軽音部に入ったと考えるべきだろう)。

そして、最終回(第12話)。このエピソードにもたらされた捻りとは、第1話の唯の登校シーンを反復するというものである。唯の独白が示しているように、第1話から最終回までの道のりが重要である。第1話の時点で唯は、自己の存在に対して少しばかりの不安(自信のなさ)を抱いていた。高校生活も1年半が過ぎてしまえば、そうした心配事も杞憂にすぎなかったことが理解される(普段は思い出されもしない小さな不安だろう)。しかし、そんなふうに思うことができるのは、時間の経過がそこにあったからだ。
軽音部に入らなかった唯の高校生活という可能世界について考えてみてもいいだろう。あるいは(同じことだが)部員が入らず、部として成立しなかった軽音部を想定することもできる。そうした可能世界からのまなざし(『ハルヒ』のいたるところに見出されるような)が『けいおん!』の世界に注がれているとしたら、どうだろうか。最終回で唯が過去を思いやるまなざしには不安を抱えていた自分に対する慈しみのようなものを見出すことができる。そして、このまなざしが『けいおん!』全体に見出され、美しい風景という形で立ち現れているように思うのである。
最終回で家から学校まで走っていく唯は、過去から現在まで歩んできた彼女自身の行程を辿り直していく。そして、辿り着いた現在の舞台上には軽音部のメンバーがいる。この箇所で、先に提示した問い、「なぜ唯は軽音部に入ったのか」が提起されていると言える。唯は軽音部に入っていなかったかもしれないし、単なるひとりの観客としてこの場で同級生の演奏を見上げているだけだったかもしれない。そうした距離感がこのシーンには見出される。だが、実際には、唯は軽音部に入り、そこで仲間と出会った。そんなふうにして唯が現在へと帰ってきて演奏を始めたあと、唯のことを遠くから見つめていた視点も彼女から離れ、部室へと移動する。

この部室のショットも、『かなめも』のことを考慮に入れると、大きな意味を持ってくる。つまり、この部室は、『かなめも』に出てきた誰もいない食卓と同じ意味を持っているのではないだろうか。ここで示されているのも、誰もいない部室である。『かなめも』において、かなは、誰もいない食卓を、いつかはやってくる別れの後の風景と見なしていた。『けいおん!』のこのシーンでは、部室の未来、つまり楽しい時間の終わりを見つめる視点人物は描かれていない。誰もいない午後の部室に暖かい日の光が差しこんでいるだけだ。だが、この光に仮託される形で、終わった地点からのまなざしが現在に注がれているように思うのである。
ここに遠さの観念が立ち現れている。こうした遠さに『けいおん!』のキャラクターたちは、気がついていない。彼女たちはただ、前を向いて充実した日々を送っているだけだ。しかし、彼女たちの頭越しに、その日常を眺めているまなざしが存在する。これをいったい誰のまなざしと考えたらいいのだろうか。「エンドレスエイト」のことを考慮に入れるなら、ここでのまなざしは、キャラクターひとりひとりのまなざしと考えるべきだろう。可能世界のキョンたちがひとつの出口を夢想したように、そしてそれがデジャヴという形で現在の風景を二重化したように、『けいおん!』に見出されるまなざしも、(おそらく未来から高校生活を懐かしく回顧した)彼女たち自身のまなざしだと考えられる。
『けいおん!』の課題。それは、人生の一回性という重荷をいかにして軽くすることができるか、というものである。この作品では、幸福な日常がただ単に提示されているだけのように見えるが、それが高校生活という短い期間にだけ(あるいは箱庭的な学園生活の中でだけ)実現しているという点もちゃんと示されているように思う。つまり、『けいおん!』で描かれている日常とは、花火と同様、一瞬の輝きでしかないのだ。
充実した日々を、それがいつかは失われてしまうという懸念を抱くこともなしに、ただただ前向きに過ごしていく彼女たち。そうした日常の輝きは、北極星のように、彼女たちの人生の道しるべになっているだろう。「兎と亀」のモチーフ(校舎の階段の手すり部分に彫像が設置されている)が示しているように、彼女たちは、前に進んだり後戻りしたり、時にはひと休みしたりしている。いったい、どちらの方向にどれだけ進んでいるのか。どの方向に進んでいるにしても、彼女たちは、気がついたらこんなに遠いところまで来てしまったという地点に到達しているだろう。そうした地点から高校生活を懐かしくも温かく振り返るまなざし。そうした遠くからのまなざしが『けいおん!』全編に注がれているように思うのである。
結論──不在の痕跡
「エンドレスエイト」は、デジャヴという仕掛けを用いることで、のっぺりとした現在の風景を複数化した。現在の風景のうちに微小なズレや亀裂を見出したとも言える。この観点を逆にして考えれば、現在の風景が直接にそのまま立ち現れることなどありえるのだろうかという疑問が生じてくる。つまり、われわれは、過去を思い出したり、未来を先取りしたりすることによって、現在の風景を常に複数化しているのではないだろうか。
アニメの画面それ自体が彼方への示唆を与えるスクリーンとして機能しているのは間違いない。アニメの世界が彼方なのではなく、それが疑似的な奥行きの感覚を与える平面として機能しているということである。そうした意味では、アニメ視聴それ自体が現在の風景を複数化することと関わっている。
京都アニメーションは、アニメというスクリーンに「現実」の風景を映し出すことによって、現在を複数化している15。『涼宮ハルヒの憂鬱』『らき☆すた』『けいおん!』といった一連の作品に見出される戦略を考慮に入れるならば、現在の日常が出口になることこそ、京都アニメーションの打ち出している方向性だろう。日常から遊離し、そしてまた、日常に戻ってくるということ。この回り道が、人生の一回性に対して、ギリギリの倫理を提出している。
「この道はいつか来た道。ああ、そうだよ。あかしやの花が咲いてる」(北原白秋作詞『この道』)。この「あかしやの花」の場所にアニメのキャラクターたちの不在の痕跡を認めること。これこそが日常系アニメの出口だろう。
著者

関連商品
関連リンク



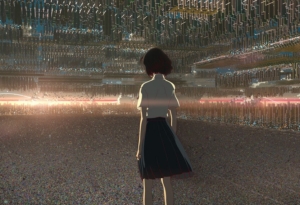

脚註
- 東浩紀+宇野常寛+黒瀬陽平+氷川竜介+山本寛「物語とアニメーションの未来」『思想地図 vol. 4』、NHK出版、2009年、202−205頁。 ↩︎
- 同種の逆転は、例えば、『ぼくのなつやすみ』(2000)というビデオゲームのバグにも見出される。この作品は、夏休みの1カ月間、田舎での楽しくも切ない生活を体験できるというノスタルジックなゲームである。本当ならば、8月31日で終了するはずなのだが、特別な操作を行うと、8月32日というありえない日を発生させることができる。ここで起こっているのは、「エンドレスエイト」で描かれているのと同様、夏休みの延長という事態である。このバグを紹介したいくつかの動画に見られるように、映像面でも様々な異変が生じ、ホラーゲームめいた様相を呈することになる。 ↩︎
- 「エンドレスエイト」は、第1回と第8回を除いて、話の展開がほとんど同じなので、それをどのような演出によって描き出すのかがひとつの注目点となっている。ちなみに第4回の演出(と絵コンテ)を担当したのは高雄統子である。 ↩︎
- こうした遠景を暗示する曲として、『AIR』の主題歌「鳥の詩」がある。冒頭の「消える飛行機雲」という言葉が象徴的であるが、彼方そのものが直接出現するということはありえない。彼方は何か具体的なものに代理される形で、遠くにあるものとして示される。そうした遠さの観念として「消える飛行機雲」というのは最適な表現だと言える。 ↩︎
- フロイト「快感原則の彼岸」(『自我論集』、中山元訳、ちくま学芸文庫、1996年、199頁)の最後に引用されているハリーリーの詩の一節。 ↩︎
- 「エンドレスエイト」についてのより詳細な考察に関しては、拙ブログの記事「「エンドレスエイト」から立ち上がってくる倫理──平行世界の確率論的な倫理について」(metamorforsis、2009年9月3日)を参照のこと。 ↩︎
- 「『けいおん!』は “仲間” を描き、『かなめも』は “孤独” を描いた」(やまなしなひび、2009年10月2日)。他に『かなめも』の特異な点に注目したブログとして、「二〇〇九年夏アニメの一番の奇作は『かなめも』だと思う」(karimikarimi、2009年10月3日[2023年8月時点では非公開])を参照のこと。 ↩︎
- この種の共同体において鍵となるのは母子関係だ、という知見が『かなめも』でははっきりと示されている。風新新聞専売所の中心にいるのは「代理」という綽名で呼ばれる小学生の少女である。彼女は、年齢に似合わない大人びた口調で話をし、新聞屋を厳しく切り盛りする。つまり、幼い少女がまるで老獪な母親のように振る舞っているわけだ。疑似的な母が中心にいるがゆえに、他のメンバーは、子供のように振る舞うことができる(甘えられる)、とひとまずは言えるだろう。だが、この関係性は時に逆転する。「代理」が年齢に見合った子供の顔を見せるとき、つまり、ある種の弱さを示すときには、他のメンバーが母代わりとなり、大人の顔になる。こうした関係性が、疑似家族的な共同体を描いたサブカルチャー作品にとって一般的であるのかどうかは、はっきりとは言えない。だが、少なくとも『かなめも』は、子供に甘える母というイメージを、共同体にとってなくてはならない要素と見なしているように思える。 ↩︎
- 日常系の裏面としての暗い領域は、二次創作という形で、補完的に表現されることがある。例えば、(ニコニコ動画に投稿されている)『らき☆すた』のMAD『こなたが周りの何気ない言葉によって傷ついてしまったようです』シリーズは、仲良しグループがはらみうる暗い領域(端的に言えば誰かの排除)を、本編の台詞を巧みに利用して、表現していた(とりわけ「ver.3」(sm605130)を参照のこと)。この観点からすれば、日常系の裏面には常に孤独の問題が潜在していて、こうした問題を免れている作品は存在しないとすら言えるかもしれない。たとえ作品の表層に孤独の影を認めることができないとしても、二次創作(言い換えれば解釈)という形で、それは回帰してくるのだ(孤独を描いた『らき☆すた』の二次創作動画として『木冬かがみが大学でぼっちになっているようです~柊かがみの週末~』(sm2909334)も参照のこと)。 ↩︎
- 『らき☆すた』が物語の水準でのまとまりを拒絶しているとすれば、『涼宮ハルヒの憂鬱』は(セカイ系の文脈を引き受けつつ、そこからの離脱を図っているという意味で)物語の軟着陸を狙った作品だったと言えるかもしれない。作品消費(受容)というレベルで言えば、YouTubeを舞台にして模倣への欲望を搔き立てたのが『ハルヒ』のダンスだったとすれば、『らき☆すた』の断片的な映像は、ニコニコ動画を舞台に、多くのMAD作品の素材を提供していた、という対比を見出すこともできる。 ↩︎
- フロイトがユーモアについて語った言葉に次のようなものがある。「いってみれば、ユーモアとは、ねえ、ちょっと見てごらん、これが世の中だ、随分危なっかしく見えるだろう、ところが、これを冗談で笑い飛ばすことは朝飯前の仕事なのだ、とでもいうものなのである」(高橋義孝訳「ユーモア」『フロイト著作集3』、人文書院、1969年、411頁)。『らき☆すた』の各エピソードで示されているものもこうした軽やかさだろう。 ↩︎
- 同種の試みを行っていた作品として、日常系ではないが、アニメ『そらのおとしもの』(2009)の名前を挙げることができる。この作品の第2話エンディングの空飛ぶパンツが当時話題になったが、これが示しているのも、一種の無意味さ(意味の軽量化)だろう。ちなみに『そらのおとしもの』は、セカイ系のパロディになっている。『イリヤの空、UFOの夏』(2001−03)に出てくるような戦闘美少女との出会いによって、日常が非日常へと変化する予感が漂う。だが、そうした物語の流れを脱線させるかのように話は進んでいく。この脱線の一例が空飛ぶパンツであり、ここではないどこかへと、遠い世界へと飛んでいくというセカイ系的な遠景のモチーフが、パンツという通俗的な物質(天使の翼とは対極にあるもの)に置き換わることによって、意味の脱落が行われているのである。『そらのおとしもの』におけるパンツの物質性について指摘している点で、反=アニメ批評「挑発するパンツ設計」(『アニメルカ vol. 1』、2010年、36頁)を参照のこと。 ↩︎
- もちろん、『らき☆すた』と同様、『けいおん!』にも、ある種の成長物語の片鱗を見出すことはできる。とりわけ、アニメ版は、シリーズのまとまりとして、最終回にまで至る展開のうちに、何かしらの変化があったことを示唆している。これは、この作品の内容からもたらされたという以上に、テレビアニメの典型的な構成から要請されたものであるように思える。テレビアニメは、たとえ原作がまだ連載中であっても、どこかで話を区切って、それなりのまとまりを示さなければならない。言い換えれば、そのシリーズが盛り上がって終わるように、話全体が構成されている必要がある。この点で、1クール全12話とか全13話で構成されるアニメにあっては、第何話が全体の中でどのような位置を占めるのかという点に関して、ほぼ定番の形式が出来上がっているのが現状である。この意味で言うなら、最終回近くの山場から(暫定的な)結末へと至る構成上の起伏に与えられた名前が「成長」だと言えるだろう。 ↩︎
- これまで「まなざし」という言葉で語ってきた事柄に関して、ここで少しばかり補足的な説明を加えておきたい。まなざしとは、端的に言って、何かを価値づける視点のことである。単にそこに何かが描かれる(対象の水準)だけでなく、それをどのように評価するのかという視点(価値づけ)があるのだ。放課後の音楽室で澪たちが演奏をし、それに唯が感動した、という記述(あるいは客観的な描写)だけがすべてではない。この光景は美しく素晴らしい、という評価が存在しているのである。この視点の存在を特に裏づけているのは、このシーンにおいて、音楽室を離れて学校のいくつかの場所を示す一連のショットだ。ここにはちょっとした距離感(唯たちの実感している充実は、他の生徒たちの活動と同程度の、ささやかなものであるといった)があるのだが、だからといって、軽音部での行為が低く見積もられているわけではない。むしろこの視点の移動は、学校全体が一種の祝福を受けている(生徒全員が特別な時間を過ごしている)ことを示している。極端な言い方をすれば、このシーンで真に描かれている対象とは、放課後の空気なのだ。 ↩︎
- 黒瀬陽平は、「新しい「風景」の誕生」(『思想地図 vol. 4』所収)において、京都アニメーションの描き出す風景について論じているが、そのときに、「インターフェイスとしての美少女」という言葉によってキャラクターの働きにも注目している。風景は、何の媒介もなしに存在するのではなく、何らかのまなざしがあって初めて成立するものだろう。そうした意味で、キャラクターは、風景にとって、まなざしの在り処を指し示す指標の役割を果たしていると考えられる。アニメの舞台となった実際の場所に行くことを俗に「聖地巡礼」と言うが、キャラクター抜きの聖地巡礼というものはありえないだろう。 ↩︎


















