※本記事には、『ゴジラ−1.0』『首』『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』(いずれも2023)の結末についての情報が含まれます。
文:杉田俊介
壊れまいとし、“壊れ” に気づいたものがまっさきに壊れる。というより壊れまいとし、世界の “壊れ” に気づいたものだけが、“壊れ” を抱える。
加藤典洋「一九五九年の結婚」『日本風景論』
…ありえない… この私が…
『葬送のフリーレン』第22話「服従の天秤」
劇場映画第3弾となる『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』(2023)の映画の真のラスト、Perfumeの「すみっコディスコ」が流れるエンドロールが終わったそのあとに、映画のスクリーンそのものが「工場=映画館」の復活した「顔」になる、いや、「首」になるということ……あのシーンの異様なねじれは何を意味していたのだろうか。そもそもあれは「誰」の首だったのだろうか。「スッテンコロコロと金属製の音」(深沢七郎『風流夢譚』)を立てて転がる首=顔? ……言うまでもなく、そこで露呈した〈真理〉とは……。
*
山崎貴監督『ゴジラ−1.0』(2023、以下『ゴジマイ』と略記)のワダツミ作戦が失敗に終わったあと、特攻する震電(旧日本海軍の十八試局地戦闘機)の機体がゴジラの口の中に突っ込んだ瞬間、その後、ゴジラの首は爆裂して海に落ちたのだったろうか。どうもそれを思い出せない。スティーヴン・スピルバーグ監督の『ジョーズ』(1975)のごとく追撃してくる前半のゴジラの口に機雷が放り込まれた時のように、顔面の部分は破壊されても、ついに首は落ちてはいなかったか。どうだったか。最後に、ゴジラが海底で復活しつつあったこと、その場面の記憶はうっすらとあるのだが……。
*
すでにわれ(々)は首なしである、カオナシである、頭と身体が分裂したトルソー(加藤典洋『君と世界の戦いでは、世界に支援せよ』)である。鏡を見られない──首がないから。未熟な自己イメージの想像的な分裂を、鏡像を通して象徴的に統合できない。だとすれば、首なしのわれ(々)の肉体はどんな夢を見るのだろうか。いや、この問いは逆さまなのだろう。首なしたちの群れの見る夢を政治的に〈イメージ〉として練り上げること、政治的かつ神学的な正しい夢を新たに産み直すこと──それは、歴史がわれ(々)に課している使命の一つなのだろうから。
*
言うまでもなく、誰かの首を落として成り上がろうとすることは徹底的に無意義であり、無意味である──父殺しも母殺しもすでに不可能であり、底無しに無意味な行いでしかない。空回りする退屈な遊戯でしかない。あらゆる首どもは地面に落ちてコロコロと転がっているのだから。泥に塗れ、腐敗し、蟹に喰われている。北野武の映画『首』(2023)が観客に突き付けているのは、そうした歴史的な〈真理〉の不気味さであり、または恐ろしさ(horror)である。このホラーな〈真理〉から目を逸らした批評や扇動や運動には、今や、何の意味もないだろう──ことに、山上徹也による安倍晋三元首相暗殺事件という決定的な〈革命〉の事後の時空においては。
*
映画『首』が露呈させたもの──権力も、忠義も、宗教も、愛も、民衆も、美や享楽さえも、全て等しく無意味である。微かに残る「首」(虚無、対象a)というフェティッシュに対する執着すらも徹底的に愚弄され、汚泥の底に沈められていく。日本的な無常観やニヒリズムにすら逃げ込めない。『ソナチネ』(1993)にありえた空虚な遊びの美のようなもの、あるいは『アウトレイジ』シリーズ(2010−17)にあった誰も逃れられない悪循環の不気味さ、そうした主題性すら『首』にはない。映画自体がごろりと即物的な感じがする。百姓や芸人や障害者も含めて──全員悪人ならぬ──「全員、阿呆」である。それはわれ(々)の現在時という歴史性のアレゴリーとしてある。
*
……個人的にいちばん笑えたのは、織田信長=加瀬亮の首が弥助=副島淳によって無造作に切り落とされるシーン(黄色い猿!)であり、あるいは、「耐え難きを耐え……」という不敬的/大逆的セリフだった……。最後の豊臣秀吉=北野武のセリフと蹴りは、北野映画なんてもうどうでもいいんだ! というメタ構造的で自己嗜虐的なビートに思えたが……。
*
《明らかに、エボシの中には、ただたんにピュアなものでは片付かない、得体の知れない不気味な欲望がある。そしてアシタカは、彼女のその奇妙に過剰な欲望にこそ共鳴し、惹かれていたのではないか。エボシは、アシタカの制止を振り切り、合理的な損得勘定をも超えて、執拗なまでにシシ神の首を狙い続ける。そして、ついには石火矢によってシシ神の首を打ち落とすことになるが、その代償として、モロによって片腕を食いちぎられる。
見つめよう。エボシの中にあるのは、神殺しと国崩しの欲望であり、天長殺し(天皇暗殺)という大逆的な欲望なのだ。そのためならば彼女は、我が身を滅ぼすのも厭わない。彼女の中にも得体のしれない狂気のマグマがあり、おそらく、サンやアシタカの無意識ともひそかに響き合う「死にたい」という衝動があるのだ。》(拙著『ジャパニメーションの成熟と喪失──宮崎駿とその子どもたち』)
*
映画館の中でしきりに思い出されたのは、深沢七郎の1960年の『風流夢譚』の「皇太子殿下と美智子妃殿下」の「スッテンコロコロ」と転がる首、天皇・皇后の首なし死体、または1970年の割腹自殺後に新聞に写真が掲載された三島由紀夫の首、あるいは1997年の『もののけ姫』のダイダラボッチの首なしの身体──そして2001年の『千と千尋の神隠し』のカオナシもまたある意味では首なしなのかもしれない──などのある種の大逆的な精神の系譜のことだったのだが……。
*
ところで……再び、『ゴジマイ』のゴジラの首はどうだっただろうか?(依然として思い出せない……) 文芸批評家の加藤典洋が論じたように(『さようなら、ゴジラたち』)、戦後の時空において天皇の権威を乗っ取り、戦争の加害者と犠牲者のどちらをも表象する「不気味なもの」として反復強迫的に回帰し続け、やがて小さくなり、かわいくなり、無害化され、ハローキティやポケモンと同じような八百万の神々になった──『シン・ゴジラ』でいえば蒲田くんはかわいい(藤田直哉『シン・ゴジラ論』)──ゴジラの首は?
*
『ゴジマイ』はその映画の全体が夢である。美しい夢である。しかしじつはそれは──これは矛盾でも何でもないが──悪夢である。戦争PTSDであり、肉体を食い千切られ(『首』の冒頭の蟹に喰われる首なし死体のように?)、あるいはゴジラサウルスに(シャチが獲物をもてあそぶように)吹き飛ばされて転がった首が見続けているだろう夢である。『首』と同種の首なしのニヒリズムにおそらく『ゴジマイ』もまた直面している。
*
『ゴジマイ』は、東京に(象徴としての)原爆が落とされて、本土決戦をやり抜いて、正面から外敵を憎み抜けたなら、戦後日本は健全なナショナリズムを獲得し、誰の命も粗末にしない利他的な国民になれるだろう、というファンタジーに振り切った──かつてひどく炎上した山崎貴監督の『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』(2019)にならえば、『ゴジマイ』はまさに「ユア・ゴジラ」にほかならない。天皇や国家に頼らず、他人の命を粗末にせず、滅私奉公を決して許さないような健全な民間のナショナリズム(という美しい夢)。
*
『ゴジマイ』は、作中で完全に「アメリカの影」を消し去っているのみならず、川本三郎/赤坂憲雄/加藤典洋/藤田直哉らが連綿と論じてきた「戦後の影」(戦死者、天皇、アジア、原水爆など)をも消し去っているかのように見えた。戦後的なものの暗喩や象徴ではなく、純粋な外敵(動物的他者)としてのゴジラ。だから人々は純粋にゴジラに対して憎悪と敵意を差し向けることができる。それはほとんど、巨大な熊の駆除のような……。ローランド・エメリッヒ版『GODZILLA』(1998)は、神聖で崇高なニッポンの怪獣ゴジラをたんなる巨大動物や恐竜のごときものにしてしまったと批判されてきたが、山崎貴の戦略はむしろエメリッヒに近い。
*
敷島=神木隆之介が戦友を見棄てたというサバイバーズ・ギルトと戦争PTSDから鬱になり、自分はじつは大戸島ですでに死んでいて、戦後の暮らしのすべては屍体になった自分が見ている夢なのではないか、と叫ぶシーンがあるが、『ゴジマイ』自体がすでに首と胴体がわかれたトルソー的屍体となったニッポンが見ている夢=ファンタジー=ユア・ゴジラであるかのように感じられる……。
船や電車やビルがひっくり返って転落していく、水に落ちて死んでいく、それが何より恐ろしい、爆弾で吹き飛ばされたり炎に焼かれたりするよりも──それが山崎貴という作家の悪夢的オブセッションなのだと思われるが(『アルキメデスの大戦』の冒頭などを想起されよ)、『ゴジマイ』が全般的に目覚めた後に想起する夢のような感じを与えるのも、そのためなのではないか……。爆風に吹き飛ばされた典子=浜辺美波がじつは生きていた、という最後のありえない展開もまた、都合のいい願望夢であるとすればすんなり腑に落ちる……。
*
とはいえ……現実がどうせ変えられない最低最悪以下の悪夢ならば、せめて、日本的人情──そんなものがあるとして──に根差した「美しい夢」を見よう、見続けよう、という感覚に対して、今はそれを否定しきれず押し返しきれない自分がいる……こうしたアジール/シェルターがわれ(々)にはどこか必要なのかもしれない、と……『ドラゴンクエスト』が夢から醒めて現実に目覚めよ、という話ではなく、むしろその逆だったように……ゲームなんて虚構だ、大人になれ、現実に還れ、などと諭すような恥知らずで非人間的な真似は絶対にしちゃいけないことなのだ!
*
それで言えば、「墜落 → 水没」という悪夢的オブセッションを当のゴジラにまで適応したのは、見事な戦略だったのかもしれない。それこそが最悪の悪夢をゴジラ自身に与えて、復讐を果たすことだったのだから。オキシジェンデストロイヤーのような原子力を超える新技術によってゴジラを倒すのではなく、海=ワダツミの力を借用することは言わばSDGs的であり、資金不足で「貧乏」な民間の人々にも可能なぎりぎりのラインであるのだろう。それは庵野秀明のタバ作戦やヤシオリ作戦のような国家総動員的な総力戦とは異なる。
*
われ(々)に必要なのは、端的に、夢である。緩慢に水没しひたすら悪くなっていく「悪い夢」から脱出する、というだけではない。高度成長期をもう一度、というような国家と資本のレトロトピアの夢、空疎で美しい夢から目覚めねばならない。たとえば『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』(2020)において、魘夢の血鬼術にとらわれた竈門炭治郎が、「家族がじつは生きていて幸せに暮らしていた」という美しく甘美な夢から覚醒するために、あえて自らの首を切り落とそうとしたように……。
たんに〈美しい〉夢では足りない。〈正しい〉夢を欲望しなければならない。政治的にも宗教的にも〈正しい〉ユートピアを欲望しなければならない──ねじれや汚れを抱えた首なし、人でなし、カオナシとして……(あえてこう言おう、正々堂々の勝負に負けて、首を切り落とされて、それでもなお生きんとする「生き汚さ」の先に、もしも、新たな革命の火種があるのだとすれば?……)。
*
『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』(以下『ツギハギ工場』と略記)は革命の映画──あるいは(反資本主義ではなく)ポスト資本主義的な映画である。資本主義のポスト(後)を葛藤しつつ夢見るような映画。古びて使い物にならなくなり、ツギハギだらけになり、無能化したゴミ=廃墟は、能力主義的な社会の中で疎外されバーンアウトした労働者たちであるよりも、むしろ今や、資本主義そのものである──。
資本主義の他に道はない、世界の終末よりも資本主義の終わりを想像することの方が難しい、と大多数の人々が無意識に信じ込んでいる中で、突然、資本主義はもうすでに死んでいる、とっくに死んでるのにゾンビのように生きているふりをしているだけだ、と突き付けられることの大いなるショック。覚醒。
*
すみっコぐらしのキャラクターたちのかわいさの中には、深い悲しみが宿されている。たとえば北極生まれなのに寒さに極端に弱い「しろくま」。痩せて理想の自分になりたい恥ずかしがり屋の「ねこ」。カッパとしての記憶を喪失して、自我の不安に悩み、自分探しを続ける緑色の「ぺんぎん?」。人間に追われて母親と離れ、恐竜であることを仲間にもカムアウトできず罪悪感を抱えた「とかげ」(加藤典洋はゴジラの末裔としてハローキティやポケモンを挙げていたが、とかげの正体は恐竜であり、成長すればやがてゴジラサウルス的な存在になるのかもしれない……)。
どのキャラクターも、社会的なマイノリティとは言わずとも、この世界の中で生きづらいメンタルを抱えた存在たちであり、弱者性を持っている。さらには食べ残された脂身部分の「とんかつ」に「えびふらいのしっぽ」、「ざっそう」や「ほこり」(!)に至っては、狂気のような無能さ、無用さが宿っている。
*
この社会から廃棄されたり、掃き捨てられたりするものたち。見棄てられるのでさえなく、そもそも人々の目に見えてすらいないのかもしれない幽霊的/ヒルコ的なものたち……。そんなすみっコたちが、この社会の周縁、すみっこに身を寄せ合って、仲間たちとの小さなコミュニティを作り、相互扶助的で相互ケア的な関係を維持していく。競争や、承認や、生産性や、能力主義とは無縁なままに。
そこには、何ができるかではなく、お互いが存在していることそのものを肯定し合うような〈否定的なものたちの共同性〉がある。キャラクターたちはいにしえの八百万の神々や付喪神のようでもある。すでにわれ(々)は現実と虚構の壁を超えて、進化するキャラたちとの新たな共存と連帯を生きはじめているのだろう。
*
『ツギハギ工場』は現代的な資本主義の形態進化を巧みに描いている。勧誘に来たくま工場長は、全員の長所をほめて、ポジティブなやる気を引き出そうとする。資本主義にとって無能な労働者なんて誰もいないんだ、と。どんな長所も無さそうな相手でも「青い!」「さくさく!」などと半ば無理矢理に肯定するのだ。おもちゃ工場はハイパーメリトクラシー/ポストフォーディズムを組み込んでいる。誰も置き去りにせず、無能な者もほめてのばし、遊びと労働が一体化し、キャラと機械が融和した透明な明るさに満ちている。そうしたポスト労働的なユートピアが、そのまま、生産性と能力主義と機械化によって疎外されたディストピアへとシームレスに反転していく序盤の、ぞっとするようなホラー。その不気味さはわれ(々)にとっても親しみ深い労働疎外の光景ではないか。
*
……ちなみに『ツギハギ工場』の無人工場の不気味さは、1990年代前半のドラえもん映画、『ドラえもん のび太とアニマル惑星』や『ドラえもん のび太とブリキの迷宮』のそれを思わせる……資本と技術の自動化と加速的暴走という主題も響きあっている。もっともドラえもん(動物型ロボット)やすみっコ(キャラクター商品)はそもそも科学技術と資本主義の産物であり、それゆえ「出口」がないのだが……。
*
『ツギハギ工場』では、かつて工場=資本主義は倒産して、機能不全に陥っており、それでも無理矢理にブルシットジョブ(本来は必要のない仕事)を捏造して、またハイパーメリトクラシー的に個々人の能力を引き出して、キャラクター産業をも自己言及的に取り込んでいく。資本主義は「ツギハギ」なのである。その中に取り込まれ、組み込まれていくすみっコたちは、それに対して、相互扶助的な小集団=共同の場を(アジール/シェルターとして)維持しながら、たとえ無意識のうちの行動であれ、現代的な資本主義の暴力性に対峙するという「大文字の政治」の問題とも関わっていく。あたかもそれ自体がツギハギの、ジグザグの抵抗のようにして。
*
資本主義の終わりのあと(ポスト)のユートピア的な社会を夢見るためには、哀悼と弔いという営みが必要になる。われ(々)が慢性的に疲弊し、メンタルを病んで緩慢にバーンアウトせざるを得ないのは、自己啓発やセルフケアによっては癒やし得ない資本主義に対する無力さのためではないか(拙稿「哀悼的正義とポスト資本主義的無能性」『情況』2023年秋号)。だからこそ、もう使い道のなくなった資本主義をちゃんと哀悼し、これまでの労苦を労わってケアしよう、ツギハギになってゴミになった資本主義を(リサイクル/リノベーションというより)社会的に組み直そう……。
来たるべきポスト資本主義的な世界においては、すべての使えないものたち、古くなって役に立たなくなったものたちもまた、水子のようにヒルコのように、天国の中に産まれ直すのかもしれない……この『ツギハギ工場』という映画そのものが、資本主義の失われた可能性に対する幻燈的で幼年期的でノスタルジー的な夢のようであり(重層化するメタジャンル性)、未来に到来すべき〈すみっコ=ごみ=無能な者たち〉の可能なるユートピアの約束であるようにも見える……。
*
(それならば、象徴的な父殺しでもなく想像的な母殺しでもないような──現代においてそれらは疑似的な自爆的反動的暴力にすぎず、現実逃避的自滅にすぎないのだから──大逆的行為とは何を意味するのか? いかにしてそれを政治神学的な革命性を帯びた摂理的暴力へと練り上げられるのか?)
*
必要なのは、われ(々)の多くがねじれを抱え、敗北を抱きしめたすみっコであること、首なし=カオナシであることの自覚である。首=顔なき者たちのデモクラシーを信じることである。繰り返し言うが、何らかの権威や統治性をもつように見える他者や先行者の首を切り落とすことにそれほどの意味はない。父殺しや母殺しは有効に機能しない。それが山上事件のあとに露呈したざらりとした歴史的現実であり、向き合うべき〈真理〉である。
*
必要なのは正しい夢を見ることである。そう主張した。美しい夢と正しい夢の違いに拘泥しよう。美しい夢は見たくない現実からの逃避になりかねない。試みるべきは、逃避ではなく一時的な撤退であり、塹壕戦である。つまり外部としての出口(exit)を探すことではなく、アジールを組み上げ、シェルターを建築することである。
あまりに過酷で残酷な現実を前にして、われ(々)は何らかの夢を必要とせざるをえない。その中で正しい夢を欲望するとは、夢から現実に目覚めるというよりも、あえて「夢よりも深い覚醒」(フロイト/大澤真幸)に潜航することである。
先ほども触れた『鬼滅の刃』の炭治郎が甘美で幸福な夢を拒絶するために自らの首を切断したこと、何度も何度もタナトス的な自決を強迫的なまでに反復したこと──しかしそれは弱肉強食でリバタリアン的な現実主義(猗窩座!)に屈服するためではなかった。現実の過酷さにどんなに打ちひしがれたとしても、失敗と弱さを深く抱きしめて、現実以上に現実的な夢の深みに達するため、正しい夢の彼方に──仲間たちと共に──手を触れるための試みだった。
*
もちろん、いつだって、たった一人で夢を見ることはできないのだ。その時、人は夢の美しさに食いつぶされてしまうから(『窓ぎわのトットちゃん』において、トモエ学園というリアリズム的かつユートピア的な教育の空間を形成した小林先生ですら、きっと……)。
解放的で幸福な〈イメージ〉のアクチュアリティをたった一人で持ちこたえることはできない。集団=共同でわれ(々)は夢を見るのでなければならない。見続けねばならない。たとえどんな葛藤や対立、内ゲバや離散集合を繰り返すとしても。あるいはまさにそれゆえに。いいかえれば、解放的で幸福な正しい夢をはっきりとした〈イメージ〉としてつかみ直すためには、それにふさわしい「すみっコ」たちの、弱さや敗北を緩衝しうる何らかの集団=共同(くらし)が形成されつつあるのでなければならない──ポスト資本主義的なユートピアへと向けた集団=共同のジグザグの、ツギハギの実践があるのでなければならない。
*
逆にいえば、小さな互助集団や自助団体を作って自分(たち)の身を守る「だけ」ではおそらく足りない。小文字のアジールやシェルターを持続可能な形で維持するためにも、大文字の政治問題や社会問題を考えなければならない。小文字のアジールやシェルターのような場所を作って自分たちを外界の圧力から守りながら、しかし、資本主義や気候変動などの「大文字の政治問題」も同時に思考し、それにどんな形であれコミットしていくこと。撤退戦のコミュニズム。ツギハギのコミュニスト。
*
加藤典洋の「敗戦後論」はしばしば誤解されている。私たちは道を誤り敗北することがある、それならば誤りを消さないまま、ねじれを抱えたままに生きればよい、捩れていないよりも捻れていたほうがマシである、と加藤は言っているのでは「ない」。少なくともそれだけではない。
罪の意識や反省だけでも足りない。罪悪感を覚えられず、恥知らずのまま、人でなしのまま(首なし=カオナシのまま)、自分を構造的に誤らせ敗北させた「世界」を「認識」せよ、と加藤は言っているのだ。「彼は、むしろ自分の「誤り」を足場に、自分を反省するのではなく、自分を誤らせたもの、世界の構造のほうを、認識しようとする」(『戦後的思考』142−143頁)。そしてそのための〈世界認識の方法〉(吉本隆明)は、奴隷的な存在の、それでも生きたい、惨めでも愚かでも生きていきたい、という欲望に根拠を持っている。虫けらの私利私欲の上に何らかの公共性を築け、とも加藤は書いた。公共性という言葉が市民主義的に過ぎるなら、ユートピアと言ってもいい。正しい、解放的な〈イメージ〉である。
*
北野武の映画『首』における首たちとは、金(貨幣)であり、そのまま糞(無)である。百姓出身の茂助=中村獅童の首も明智光秀=西島秀俊の首も等しく無意味であり、等価交換されうる。偽物(影武者)の首がどんどん増殖し、汚れて誰の顔かわからなくなり、そしてごみ山のように無造作に積まれた首首首首首……。豊臣秀吉=北野武は苛立たしげに首を蹴り飛ばす。だがそれは資本主義というシステムそのものを蹴り飛ばすことだっただろうか。その一撃すらも、痙攣的(フランコ・ベラルディ)なやけっぱちの暴発にすぎなかったのだろうか。
著者
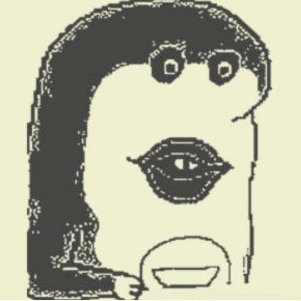
杉田 俊介 SUGITA Shunsuke
批評家。『対抗言論』編集委員。























