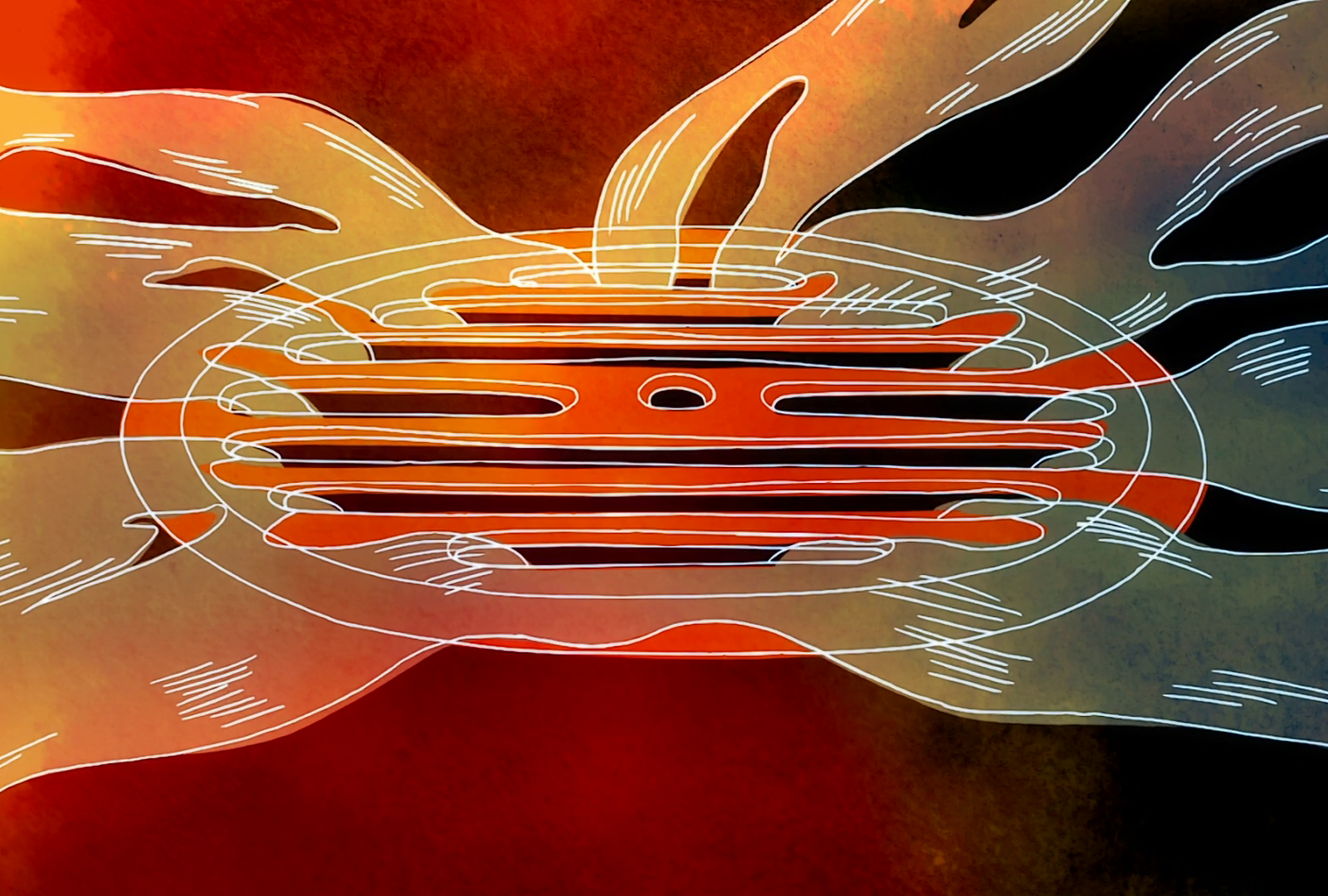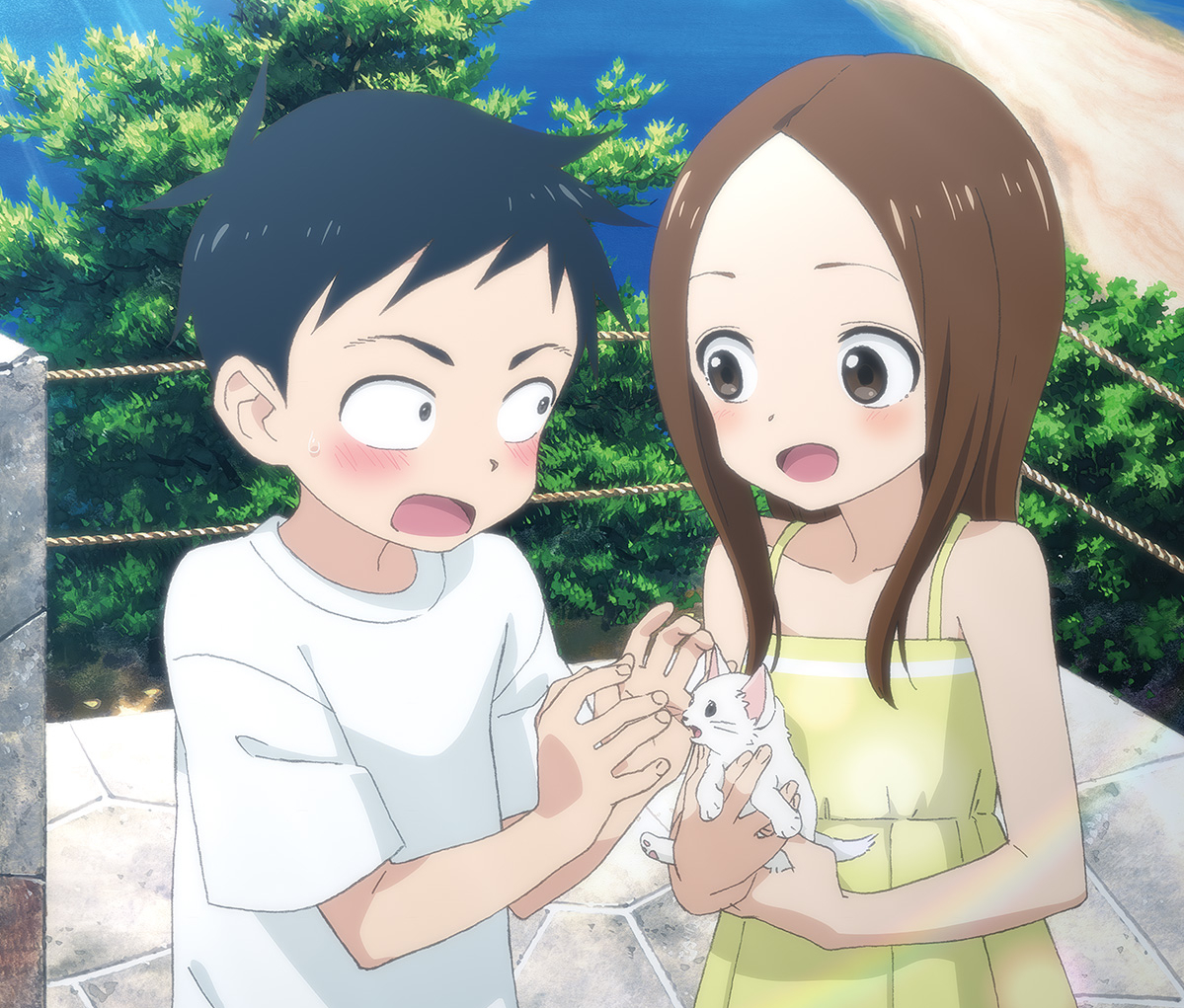※本記事は、『アニクリ vol.12 ジャンルのリフレーミング』(アニメクリティーク刊行会、2021年)所収の「母と子の物語──「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」についてのラフスケッチ」を大幅に加筆・修正のうえ、転載したものです。
文:てらまっと
以前、なかば冗談で「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」という言葉を提唱したことがある。「ヌーヴェルバーグ(Nouvelle Vague)」とは本来、フランス語で「新しい波(New Wave)」のことだ。1950年代後半から60年代にかけてフランスで勃興した新たな映画の潮流を指す言葉で、ジャン゠リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォー、エリック・ロメールなど錚々たる映画監督が含まれる。
「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」もまた、ラブコメ漫画やアニメにおける「新しい波」を名指そうとする試みだった。さしあたって私が念頭に置いていたのは、たとえば『からかい上手の高木さん』『宇崎ちゃんは遊びたい!』『イジらないで、長瀞さん』といった主に男性向けのラブコメ漫画だ。連載開始時期にはややばらつきがあるものの、いずれも大きな人気を博し、2010年代末~20年代初頭には相次いでテレビアニメ化されている。とりわけ「ヌーヴェルヴァーグ」の火付け役とも言うべき『高木さん』(2013–)の影響は絶大で、しばしば「ジェネリック高木さん」1とも揶揄される一群のフォロワー作品を生み出した。『宇崎ちゃん』や『長瀞さん』(ともに2017–)も、この系統に分類されることが多い2。
ただ「ヌーヴェルヴァーグ」といっても、原作人気からアニメ化までのタイムラグを考えると、私の認識が一周以上遅れている可能性は否定できない。『高木さん』をはじめとするラブコメ作品が「新しい波」として押し寄せたのは数年前のことで、もしかしたらいまではもうとっくにピークを過ぎて引き波に変わりつつあり、沖合ではまったく別の波が育ち始めているのかもしれない。けれども、これらの作品がラブコメというジャンルの大海に消えてしまうまでには、少なくともまだ1年ほどの猶予がある。原作漫画はいずれも快調に連載中だし、2022年には『高木さん』のテレビアニメ第3期の放送(1–4月)と映画の公開(6月)が予定されているほか、同年中に『宇崎ちゃん』の第2期も放送されることになっている。2021年春にアニメ化されたばかりの『長瀞さん』も、早々に第2期の制作が決定した。彼女たちが市場からの引退を迫られるのは、たぶんもう少し先のことだろう。
この試論は、いつか書かれるはずの浩瀚な「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ論」に関するアイデアスケッチのようなものだ。怠惰な私よりも先に誰かが書いてくれるかもしれないし、もしかしたらすでに書かれているのかもしれないが、いずれにせよ現在の私には、先に挙げた諸作品について詳細な議論を展開するだけの準備が整っていない。ただぼんやりとしたアイデアが脳裏に浮かんでいるだけだ。それでも、この大雑把なイメージをあえて言語化してみると、だいたいこんなふうになるだろうか──「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」は “母と子の物語” である。
“逆攻略” される男性主人公
若い男女の恋愛を描いたラブコメが「母と子」の物語とはどういうことだろうか。この疑問に答える前に、まずは「ヌーヴェルヴァーグ」作品のざっくりした共通点と大まかな物語構造を押さえておこう。これらのラブコメ作品に共通するのは、タイトルにヒロインの名字が入っていることだけではない。高木さんも宇崎ちゃんも長瀞さんも、ときに「S〔サディスト〕系女子」3と形容されるほど、男性主人公に対して挑発的(あるいは攻撃的)なアプローチを仕掛けてくることに大きな特徴がある。ヒロインの可愛らしさのみならず、彼女たちの執拗な「からかい」や「イジり」や「ウザ絡み」を受けて狼狽したり赤面したりムキになったりする男性主人公の滑稽な振る舞いも、これらの作品の大きな見どころのひとつだ。
もちろん、ヒロインによるこうした過激なアプローチの背後には、恋愛に消極的な男性主人公に対するひそやかな──読者・視聴者にとってはあからさまな──好意がある。「好きの反対は無関心」とはよく言ったもので、彼女たちは男性主人公が嫌いだから攻撃的な言動を繰り返しているわけではない。そうではなく、逆に相手のことが大好きだからこそ、わざとからかったりイジったりウザ絡みしたりして気を引こうとするのだ。いわゆる「好きだからつい意地悪したくなっちゃう」というやつである。当初はヒロインに翻弄されるばかりだった男性主人公も、やがてまんまと彼女たちの術中にはまり、次第に相手のことを恋愛対象として意識するようになる。つまり「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」とは、ごく単純化して言えば、奥手な男性主人公がヒロインに “逆攻略” されていく物語なのだ。
私の知るかぎり、ある時期からの男性向けラブコメ作品には、基本的に男性主人公のほうからアプローチして意中のヒロインを攻略していくか、あるいは対等に近い関係で相互に距離を縮めていくものが多かったように思う。とりわけ「美少女ゲーム」の影響力が強まった1990年代末以降は、たとえば『ラブひな』(1998–2001)に典型的に見られるように、複数ヒロインによるハーレム展開と男性主人公の選択=決断(告白)がそれなりに重要な役割を担っていた。もちろん例外もたくさんあるが、とはいえ『高木さん』に代表されるような、勝ち気な単独ヒロインによる逆攻略のプロセスそれ自体を主題的に描いた作品群が、これほど多くの支持を集めたことはなかったはずだ。それらを冗談交じりに「ヌーヴェルヴァーグ」と称する所以である。
「男らしさ」の終焉?
ところで、この「新しい波」がにわかに打ち寄せた背景には、個々の作品固有の魅力を別にすれば、ある社会的要因を挙げることができる。その要因とは、現代の日本社会における「男性性の困難」とでも言うべきものだ。本稿では細かい議論は省略するが、要するに、かつては美徳とされていた「男らしさ」を支える社会的・経済的条件が崩れ、むしろフェミニズム的な批判の対象となったことで、自らの潜在的な加害性やコミュニケーションにおける暴力性に敏感な男性が増えた(とされている)ことである。恋愛などの濃密な人間関係を回避しようとする、いわゆる「草食系男子」もその兆候のひとつに数えられるかもしれない4。「ヌーヴェルヴァーグ」作品を特徴づける恋愛に消極的な男性主人公は、さしあたってこうした「男性性の困難」をストレートに体現しているように見える。
もちろん、そんな大げさな理由を持ち出さなくても、ヒットの要因は他にも考えられる。たとえば『高木さん』や『長瀞さん』には、かつて同年代の女性に手ひどくからかわれた、イジられたという一部男性のトラウマを「好きだからつい意地悪したくなっちゃう」という心地よいファンタジーによって改竄し、想像的に癒やしてくれる効果もあるのかもしれない。いずれにせよこれらの作品では、男性主人公は自らの潜在的な加害性におびえながらも──「またからかわれるかもしれない」「キモがられるかもしれない」──、おそるおそる、だが着実にヒロインとの仲を深めていく。それもこれもすべて、彼女たちのほうから積極的にアプローチしてくれるおかげなのだが。
このように整理すると「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」は、臆病な男性主人公をほとんど理由もなく慕ってくれ、少々過激な仕方ではあるが引っ張っていってくれる、じつにうらやま……都合のよいヒロインが登場する作品群に見えるかもしれない。もちろん、フィクションなんてそもそもご都合主義的なものだから、そのこと自体をここでとやかく言うつもりはない。むしろ私が注目したいのは、そのような「都合のよい」物語を生成し、駆動させている構造それ自体のほうだ。そしてこの構造こそが、私の考えでは、先に述べた “母と子の物語” なのである。
挑発による「成長」の促進
「母と子」といっても当然、ヒロインと男性主人公が作中で親子関係にあるわけではない。これはあくまでメタファーであり、彼女たちが部分的に「母」のような役割を担っていることを表現するレトリックにすぎない。ここでいう「母」の役割とは、具体的には男性主人公を「教育」したり「成長」させたりする振る舞いを指している。私の見るかぎり、この傾向は『高木さん』や『長瀞さん』でとくに顕著で、彼女たちの度重なる「からかい」や「イジり」を受けているうちに、当初は翻弄されるだけだった男性主人公が少しずつ「成長」しているように見えるのだ。実際、劇場版『高木さん』の監督を務める赤城博昭は、あるインタビューで次のように答えている。
高木さんが可愛いというのはもちろんあるのですが、西片くんの成長を描こうとしてきました。西片くんをただのいじられキャラで終わらせず、成長を描こうとしています。高木さんの笑顔は、西片くんだけに見せる表情です。そのリアクションを大切にしています。高木さんを愛するようになる西片くんを大切に描いていこうとしています5
赤城監督が明言しているように、『高木さん』では男性主人公・西片の「成長」が描かれる。そしてとりわけ重要なのは、彼の成長がもっぱら高木さんの「からかい」によって誘発・促進されていることだ。ここでは私の準備不足のせいで具体的な描写の細部には立ち入れないが、このフォーマットは基本的に『長瀞さん』『宇崎ちゃん』にも共通している6。「ヌーヴェルヴァーグ」作品の男性主人公たちは、ヒロインによる挑発への対応を通じてだんだんと自信をつけ、見失っていた「男らしさ」を回復していく。要するに、彼女たちの攻撃的な言動は男性主人公をして「男性性の困難」を克服せしめるための、つまりは「成長」させるための一種の加圧トレーニングとして機能しているのである。
たしかに「ヌーヴェルヴァーグ」作品のヒロインは最初から男性主人公を慕っており、それゆえにしつこくからかったりイジったりウザ絡みしたりする。けれども、だからといって彼女たちは自分からすぐに愛を告白するわけではない。それでは物語が終わってしまうからだが、もっと本質的な理由として、男性主人公が自分の好意に気づき、自分のことを好きになり、いずれは彼らのほうから決断(告白)してくれることを彼女たちが暗に期待しているからだ。そういう意味では、彼女たちは “ありのまま” の男性主人公を愛しているわけでは決してない。そうではなく、彼らがいつの日か男らしく自分の手を引いてくれるはずだという将来性を見込んでいるからこそ、露骨に挑発的=教育的なアプローチを繰り返すのである。

©2019 山本崇一朗・小学館/からかい上手の高木さん2製作委員会
それゆえ、これらの作品では──「ヌーヴェルヴァーグ」という呼称とは裏腹に──むしろオールドスクールなラブコメ作品に見られるような、男性側が主導権を握る、あるいは握らされる恋愛プロトコルへの復帰が目指される。女性と自然に会話し、ときに容姿や服装を褒め、休日にはデートに誘い、悪漢やナンパ男を退け、やがて愛を告白する──こうしたステレオタイプな手続きを適切に処理し、自分を “攻略” してもらうためには、恋愛に消極的な男性主人公に「男らしさ」を強制インストールしなければならない。あたかも自分の息子を理想の男性に育て上げようとする過保護な母親のように、彼女たちは「からかい」や「イジり」や「ウザ絡み」を通じて、臆病な男性主人公をひそかに「教育」していくのだ。
自立と依存のパラドックス
評論家の宇野常寛は、かつて高橋留美子の記念碑的なラブコメ漫画『うる星やつら』(1978–1987)を「母性のディストピア」と評したことがある7。男性主人公をドタバタラブコメの楽園に閉じ込めて「成熟」の可能性を奪い、独占的に支配しようとする「母」のごときヒロインと、そこに依存する未熟な男性主人公(宇野の言い方では「矮小な父」)の共犯関係を名指したものだ。
こうした重力圏からの脱出を強く志向する宇野にとってみれば、なるほど「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」に息づく母性は、高橋作品のそれよりもさらに肥大化した「ウルトラ・ディストピア」に見えるだろう。色恋にうとい主人公を捕まえ、自らの好みの男性へと育て上げ、やがては生涯の伴侶にしてしまう8のだから。そこに男性主人公の主体的な選択の余地はない──というより正確には、彼らはまさに「母」としてのヒロインに「教育」されることで初めて一人前の男性に、つまりは近代的な個人としての “主体” になることができる。そして彼女たちの思惑どおり、自らの自由意志によって告白し/告白させられ、彼女たちを伴侶に選ぶ/選ばされるのである。
ここには明らかにパラドックスがある。当人にとっては自立的な振る舞いのはずが、結果的にきわめて依存的な関係を招いてしまうというパラドックス。宇野が繰り返し告発する「母性のディストピア」とは、まさにこのようなものであるにちがいない。近代社会が要求する「自由で自立した個人」を信奉する人々にとっても、「ヌーヴェルヴァーグ」作品に充満する母子の共犯関係は、およそ耐えがたいものに映るかもしれない。
けれども私自身は、むしろこうしたパラドックスに、すなわち “母と子の物語” にこそ積極的な意味があると考えている。高木さんも宇崎ちゃんも長瀞さんも、いわゆる「オタクに優しいギャル」と同様、現実世界ではありそうもないフィクショナル・キャラクターにすぎない。世の多くの男性が経験するように、かつて私の趣味をからかってきたあの子も、私の容姿をイジってきたあの子も、残念ながら私のことが好きだからそうしたわけでは全然なかった。しかしだからこそ、高木さんや宇崎ちゃんや長瀞さんといった代償的なキャラクターが成立しうるのであり、私を含む多くの男性読者=視聴者を魅了することにもなる。
「ヌーヴェルヴァーグ」作品がこれほど多くの支持を集めたのは、ヒロインの造形がリアルだったからではない。これらの作品は恋愛の教科書として読まれるべきではないし、実際にそのように読む人もほとんどいないだろう。彼女たちは言ってみれば、あらかじめ失われた過去、断念された夢、恋い焦がれた幻であり、この荒涼とした砂漠の裏側にある補色に彩られた存在なのだ。
「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」はこのような意味で、徹頭徹尾 “現実” から切り離されている。にもかかわらず、というよりだからこそ、彼女たちは意中の男性主人公に対してだけではなく、この社会それ自体に対してもまた、優れて挑発的=教育的な装置、あるいは「母胎」として機能しうる。というのも私の考えでは、そもそも「自由で自立した個人」という近代の輝かしい理念そのものが、いまやこうした荒唐無稽なフィクションによって支えられ、あまつさえ生み出されてもいるからだ。
近代的個人のマトリックス
理念それ自体がフィクションにおいて生み出されるとはどういうことだろうか。ここで私が具体的に念頭に置いているのは、いまから30年以上前に公開された劇場用アニメ『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984)である。言わずと知れた押井守監督の代表作のひとつであり9、文化祭前日をループし続ける夢の世界からの脱出(の不可能性)を描いた批評的な作品として、今日でも高く評価されている。このなかで押井監督は、メインヒロインのラムに追いかけ回される男性主人公・諸星あたるに、ある印象深いセリフを語らせている。物語の最終盤、ラムの面影を感じさせるミステリアスな少女に対し、あたるは独り言のようにこうつぶやく。
お兄ちゃんはね、好きな女を好きでいるために、その女から自由でいたいのさ。わかんねぇだろうなぁ、お嬢ちゃんも女だからなぁ……。

©1984 東宝 ©高橋留美子/小学館
この逆説的なセリフは一見すると、浮気性の男性の身勝手な弁解とも、素直になれない不器用な恋心とも読める。あるいは現在なら、女性蔑視的な発言として批判にさらされるかもしれない。実際、インターネット上にはそのような感想がいくらでも転がっているが、私の見るかぎり、それらが的を射ているとはあまり思えない10。
「好きな女を好きでいるために、その女から自由でいたい」という奇妙なロジックは、むしろこれまで論じてきた「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」の文脈に即して考えることで、きわめて明瞭に理解することができる。つまり、自らの自由意志で、自らの主体的な選択として「好きな女を好きでいる」ためには、その女の求愛に応じてはいけない。なぜなら応じてしまった瞬間、あたるはラムの重力圏──「母性のディストピア」──に完全に取り込まれ、先に述べた自立と依存のパラドックスに陥ってしまうからだ。そこではもはや、あたるがラムを好いているのか、ラムがそうなるように仕向けているのかわからない。このパラドックスを避けるためには、たとえば依存先をできるだけ分散する11、すなわちより多くの女の尻を追いかけ続けるしかない。
けれども、ここでもうひとつ注目したいのは、まさにこのような臨界点において初めて、あたるが「自由」という言葉を口にすることだ。彼はすでに「好きな女」の重力に相当程度引きずられており、だからこそ「その女から自由でいたい」という願望も生まれてくる。つまり、あらかじめ「自由で自立した個人」としての男性主人公がヒロインに籠絡され、依存させられていく──あるいはそこから逃げ回る──のではなく、まさにそうしたせめぎ合いのなかから、まるで渦のように「自由」の観念が、あるいは「自由で自立した個人」という理念そのものが発生してくるのである。
そもそもラムがいなければ、あたるはたんなる浮気性の女好きにすぎない。彼が偉そうに「自由」を云々することができるのも、虎柄ビキニを穿いて空を飛び、語尾が「~だっちゃ」の美少女宇宙人という、およそリアリティのないフィクショナル・キャラクターに愛されているおかげである。そして私の考えでは、ほかならぬこの点に、現実から切り離されたフィクションの「母胎」としての意義がある。ラムに追いかけられるあたるが、あるいは高木さんや宇崎ちゃんや長瀞さんに執拗に絡まれる男性主人公たちが教えてくれるのは、まさにこれらのフィクショナルな「母」こそが、いまや「自由で自立した個人」の可能性の条件でもあるということなのだ。自立と依存とが混ざり合う、そのようなパラドックスのただなかにおいてひとつの理念が生成するのであり、彼女たちはまさにそこに向かって彼らを産み育てるのである。
もちろん『ビューティフル・ドリーマー』と「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」とのあいだには、無視すべきではない違いもある。両者のあいだに横たわる30年余りの歳月は、男性主人公の言動をほぼ180度変えてしまった12。「男らしさ」は美徳から悪徳へと転落し、女の尻を追いかけるどころか、人間関係へのコミットそれ自体を躊躇するような傾向さえ生まれた。ヒロインによるアプローチがストレートな求愛から挑発へと転換したのも、時代の変化をあけすけに反映しているように見える。
にもかかわらず、そこには依然としてひとつのミッションが受け継がれており、あたかもこの使命を保持するためにこそ、ヒロインと男性主人公との関係性がその時々の社会に応じて移り変わっていくかのようだ。自立と依存をめぐるパラドックスを胚胎し、そのせめぎ合いの果てに「自由で自立した個人」に呪われた未熟児を産み落とすこと──「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」に託されているのは、まさにそのようなマトリックスとしての役割にほかならない。それはあの文化祭前日から、いやおそらくは先の戦争に敗れたその日から、ひそかに引き継がれてきた使命なのだろう。
生の慰めとしてのフィクション
とはいえ、このように述べたところで、宇野の主張する「母性のディストピア」批判を回避したことにはならない。彼は一貫して「ディストピア」からの脱出を主張し、肥大した母性と矮小な父性との結託を告発し続けてきた。なるほど、現実においてはまさにそのような構造こそが女性を「母」として家庭に縛りつけ、差別的な性役割を再生産してきたにちがいない。「好きな女を好きでいるために、その女から自由でいたい」という先のあたるのセリフは、一方で「成熟」を唱えながらも、他方で自らの妻を殴り続けた批評家・江藤淳の振る舞いを否応なく想起させる。
しかしだからといって、たとえば高度な情報技術に支えられたフラットな人間関係が “母と子の物語” を代替しうるとは私にはとても思えない。もちろん、高いコミュニケーション能力に恵まれた「強者」なら、かつてあたるが試みたように依存先を絶えず分散させることで、相対的に「自由で自立した個人」として振る舞うことができるだろう。だが、そんな連中は本来的にフィクションを必要としないのであって、そもそも論じるに値しない。むしろ私が問題にしたいのは、まさにそのようなコミュニティから脱落し、あるいは排除される「弱者」こそが、しばしば自分自身も巻き込んだ破滅的な行為に走りうるということだ。最新のテクノロジーもフラットなコミュニケーション環境も、彼らが自らを救う手立てにはなりえない。なぜなら、彼らはまさにそれらから/それらによって疎外されているからである。
こうした問題を緩和するためには、結局のところ、地道に社会保障制度を充実させていくしかないのかもしれない。それはこの国にあっては気の遠くなるような作業であり、そのあいだにもさまざまな悲劇が繰り返されるだろう。最新の情報技術に支援された「新しい主体」によるドラスティックな社会変革のビジョンを信じるには、私はいささか年をとりすぎてしまった。私の目には、もはやそのような「オルタナティブな成熟」への志向そのものが、母の膝で遊びながら「その女から自由でいたい」男性的な欲望のひとつのヴァリアントに見えてしまう。
やがてより良い社会が実現するのかどうか、私にはわからない。もっと悪くなる可能性のほうが高いのかもしれない。いずれにせよその道行きには、すでにおびただしい数の死体が積み重なっており、また刻一刻と積み上がっていく。腐臭に鼻をつまみ、顔をそむけてなんとか歩いてきた私も、いつの日か彼らの仲間に加わるだろう。そうやって死にゆく者たちの心を慰めるのは、私たちの生前にはついぞ到来しなかった輝ける共産主義社会でも、新たなるキリストでもない。そうではなく、童話の「マッチ売りの少女」がマッチの火のなかに幸福の幻影を垣間見て死んでいったように、いまやフィクションこそが、ユートピアへの途上で野垂れ死ぬ私たちの生の惨めさを贖いうるのである。たとえその慰めが、少女を死に至らしめる資本主義システムによって与えられた商品の輝きにすぎないとしても。
人は何者かに依存することで初めて、自由に生きようとすることができる。江藤の、ひいては大多数の人間の過ちは、このパラドキシカルな役割をもっぱら現実のパートナーに要求したことにあった。生身の人間に「母」の役割を押しつけるのは端的に暴力であり、ハラスメントであり、人権侵害である。であればこそ、現実に多様な依存先を確保することのできない者たちにとっては、およそリアルとは言いがたいフィクショナル・キャラクターこそが代理的な「母」、すなわち「自由で自立した個人」のマトリックスとなりうる。
革命が頓挫し近代が座礁したこの国で、私たちはご都合主義的なフィクションに依存することで初めて、このどうしようもない現実に踏みとどまることができる。存在しないヒロインにからかわれ、イジられ、うざ絡みされる──とはつまり想像的に「ケア」される──ことで初めて、あたかも「自由で自立した個人」であるかのように振る舞うことができる。「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」が体現しているのは、言ってみればそのような母性の人工楽園であり、非現実的であることにその最大の美徳がある。しばしば投げかけられる「現実逃避」という批判は、まず何よりも、この現実が誰にとっても生きるに値するものだと無邪気に信じている者たちへと差し戻されなければならない。
「ラブコメ・ヌーヴェルヴァーグ」の男性主人公はおそらく全員、彼らを産み育ててくれたヒロインと結ばれるだろう。その微笑ましい光景をまぶたの裏に焼き付けながら、私たちは裏切りと寝取られに満ちた荒涼たる砂漠を歩んでいく。生の意味も目的もたやすく見失われる時代にあって、我が内なる高木さんの「からかい」だけが、夜空の星辰のごとく行く手を照らしている。
著者

てらまっと teramat
「週末批評」管理人。志の低いアニメ愛好会(低志会)メンバー。〈バーチャル美少女セルフ受肉アニメ批評愛好家〉として労働の合間にアニメを見る日々。
Twitter:@teramat
Blog:てらまっとのアニメ批評ブログ
Twitcasting:てらまっとの怒られ☆アニメ批評
関連商品
関連リンク


脚註
- たとえば以下のまとめサイト記事などを参照。「【悲報】『からかい上手の高木さん』のインスパイア漫画、流石に多すぎる」。 ↩︎
- 『長瀞さん』に関しては、pixivでの最初の投稿「長瀞さんと先輩」(2011)が『高木さん』連載開始よりも早いため、厳密に言えば『高木さん』フォロワー作品に分類するのは適切ではない。 ↩︎
- 「高木さん、宇崎ちゃん、長瀞さん…女子も好きなコに意地悪したい!甘口から辛口まで【S系女子】まとめ」。 ↩︎
- ただし、若者が全体として「草食化」しているかどうかは議論の余地がある。たとえば以下の記事などを参照。「『若者の草食化』は本当か?40年間の『性行動調査』から見える事実」「『草食系男子の増加』という大いなる勘違い:実はバブル世代でも7割に彼女はいなかった」。 ↩︎
- 「劇場版「からかい上手の高木さん」:「せりふなきせりふ」 西片の成長を丁寧に描く 赤城博昭監督が語る魅力」。強調は引用者。 ↩︎
- ひとつだけ具体例を挙げると、『長瀞さん』の主人公である「先輩」は長瀞さんの度重なる「イジり」の結果、眼鏡を外してコンタクトレンズを着用するようになる。この一見ささやかな変化は、長瀞さんにイジられて狼狽したときに眼鏡を触る「癖」からの脱却を意味しているという点で、眼鏡ユーザーである私にはとくに衝撃的だった。彼はもはや、過酷な現実に対する「防御壁」としての眼鏡を必要としないのだ。 ↩︎
- 宇野常寛『ゼロ年代の想像力』(ハヤカワ文庫、2011年)第10章「肥大する母性のディストピア」および『母性のディストピアⅡ 発動篇』(ハヤカワ文庫、2019年)第5部「押井守と映像の世紀」を参照。 ↩︎
- よく知られているように『高木さん』には、2人の結婚・出産後の物語を描いたスピンオフ漫画『からかい上手の(元)高木さん』(2017–)がある。 ↩︎
- ちなみに私が『ビューティフル・ドリーマー』をきちんと鑑賞したのはごく最近である。このときの感想は以下の動画で語っている。「【低志会】うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマーを語る回」。 ↩︎
- 思想家の東浩紀は『セカイからもっと近くに──現実から切り離された文学の諸問題』(東京創元社、2013年)の第3章で押井守について論じているが、そこでは件のあたるのセリフを「夢のなかに永遠にいたいという宣言」として解釈している。他方で宇野は『母性のディストピアⅡ 発動篇』のなかで、同じセリフを「不可視の外部へと脱出しようとする」態度表明として理解する。このような対照的な解釈が生じうるのは、まさに依存と自立とが入れ替え可能なかたちで絡み合っているためであるように思われる。 ↩︎
- 障害の当事者研究で知られる熊谷晋一郎は、自立とは依存しなくなることではなく、依存先を増やしていくことであると指摘している。たとえば以下の記事を参照。「自立とは「依存先を増やすこと」」。あたるとほぼ同じ行動原理の男性主人公として、ラブコメに分類できるかはわからないが、たとえば「ルパン3世」を挙げることができる。 ↩︎
- 2022年10月からは『うる星やつら』の新しいテレビアニメが始まるが、仮に当時のキャラクター設定がそのまま踏襲されるとしたら、中高年ファンのノスタルジー以上の意味を持ちうるかどうかが焦点のひとつになる、かもしれない。 ↩︎