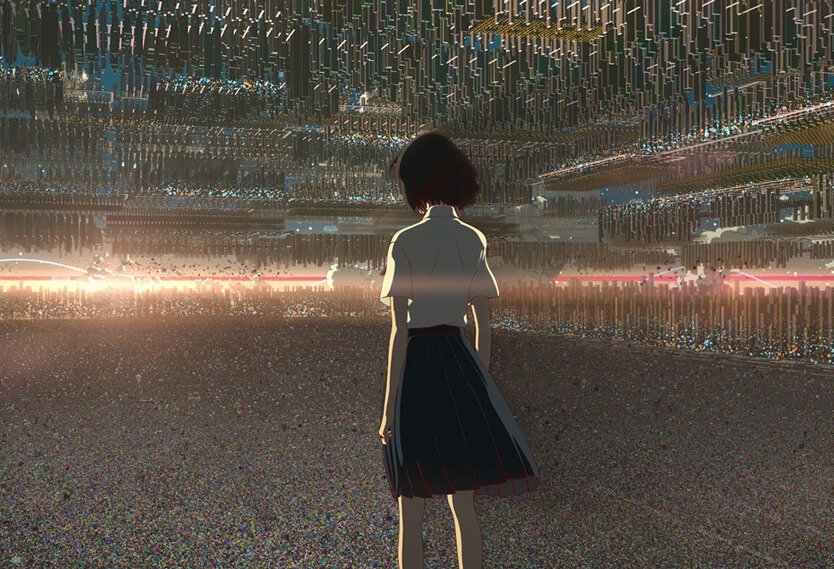現代社会では「痛み」が娯楽の定番になりつつある、と映画評を手がけるnoirseは指摘する。なぜ人は進んで痛みを消費するのか、そこにはどのような効能があるのか。ユダヤ系のいとこ同士がホロコーストの記憶をたどるロードムービー『リアル・ペイン〜心の旅〜』(2025)の読解を通じて、「心地よい」痛みを求める現代のアイロニカルな心性をえぐり出す。
文:noirse
痛みの時代
まずはちいかわの話をしたい。もともとはツイッター(現・X)にアップされた「なんかちいさくてかわいい」キャラクターだったが、誕生から4、5年のあいだに人気は拡張し続けていて、アニメや各種グッズ、大企業とのコラボや大規模展覧会、さらには「ちいかわパーク」開園と、その勢いはとどまることを知らない。ハローキティやポムポムプリン、たれぱんだやリラックマなど、ファンシーキャラはたくさんいたが、それらビッグネームと比べてもここまでの急成長は驚くべきことに思える。
では過去のサンリオやサンエックスのキャラクターと比べて、ここまで急速な成功を収めた理由はどこにあるのか。ライターの戸部マミヤはこのように述べる。
「かわいい生き物がかわいそうな目に遭っている姿」それ自体を楽しんでいる人もいるでしょう。少なくとも作者のナガノさんはそうだと思いますし、告白してしまうと私自身も今ではちいかわが不幸に見舞われる展開が楽しみで仕方ありません。1
たしかに、ちいかわほど過酷な状況に身を置くファンシーキャラクターはあまりいないだろう。そして彼らが追い詰められていく様を消費者が嗜虐的に楽しんでいるというのも間違いあるまい。

出典:https://x.gd/TBs6r
加えて戸部は「人間は不幸をエンタメとして楽しめる醜い生き物」とも補足する。まったくその通りで、ツイッターでは「不幸をエンタメとして楽しむ」ことが常習的に行われている。もちろんちいかわについてはキュートアグレッションの一種とも言えるし、シャーデンフロイデ──他人の不幸を楽しむ感情──もめずらしいものではない。けれどもちいかわ人気は、一般的にはネガティブなものとして忌避されがちな感情が以前よりも希求されていることの一例にも思える。
たとえば『呪術廻戦』(2018–24)だ。個々の呪術師の凄惨な過去が彼ら自身に呪いとなってのしかかっていくが、それが悲痛であればあるほど読者が深く共感し、作品にのめり込めるように巧みに構成されている。またこの作品は呪いにどのように対応していくべきかという問いに重点を置いているが、そのようなマンガが絶大な支持を得たのも、不幸や呪いといったものを何らかのかたちで「消費」したいと望む風潮の証左でもある。
逆に2022年の映画『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』では、人類から痛みの感覚が消え去った近未来を舞台にしている。けれども人々はかえって失った痛みを求めるようになり、自傷行為や他者を物理的に傷つけることに夢中だ。主人公も臓器摘出の手術を公開する人気アーティストで、これらは実に示唆的に思える。脚本を書いたのは1998年だったそうだが、監督のデヴィッド・クローネンバーグは複数のインタビューで、「かえって今のほうが現代性を帯びたように思う」と発言している。
もうひとつ映画を例に取ろう。『ドライブ・マイ・カー』(2021)では、妻が突然病死し、その後彼女が生前に浮気していたことを知った主人公が、終盤で「ぼくは正しく傷つくべきだった」と振り返る。本作は国内外で多数の賞に輝いたが、傷つくことでさえも「正しさ」が求められると示唆するこのセリフは特に注目された。
しかし、たしかにこれは正しくないだろうという傷つきかた──極端に言えば、テロに走るような──もあるだろうけれども、人間のもっとも私的な領域である「傷つくこと」にまで正しいか否かをジャッジしていくのは、あまりに息苦しいようにも感じられる。だがそうも言っていられないほど今は「痛み」が氾濫しており、どう傷つくかについても個々で「正しく」対処してほしい、そのような時代であることの表れでもある。
このように昨今では「痛み」の消費が日常的に行われたり、「痛み」を娯楽として提供する作品が求められたりしていて、「痛みのエンターテインメント化」もしくは「痛みの時代」と呼べるような様相を呈している。現在、多くの人がより傷つくことを、「痛み」をほしがっているのである。
ランチ付きのホロコースト・ツアー
本当の痛み(real pain)とは何だろう〔…〕わたしが演じた人物のように、薬でコントロールできるような強迫性障害の痛みはそれに当てはまるだろうか。キーランが演じた人物のように、心が耐えうる最大級の苦しみを経験していたとしても、ある程度恵まれた生活を送っている場合、それは本当の痛みと言えるのだろうか。それとも戦争や大量虐殺、そして集団トラウマの痛みだけが当てはまり、本当の痛みと認められるべきなのか。2
俳優ジェシー・アイゼンバーグによる、監督第2作『リアル・ペイン〜心の旅〜』についてのインタビューでの言葉だ。ユダヤ系アメリカ人のいとこ2人が、ホロコーストを逃れてアメリカに渡ってきた祖母の故郷ポーランドを巡るツアーに参加するというロードムービーで、第97回アカデミー賞では脚本賞と助演男優賞にノミネート。アイゼンバーグが主人公のデヴィッド、キーラン・カルキンがいとこのベンジーを演じ、カルキンが助演男優賞を受賞した。
『リアル・ペイン』は傷つく心、つまり「痛み(ペイン)」を主題にしていて、「本当の痛み」とは何か観客に問いかけてくる──というと重苦しく聞こえるかもしれないが、テンポよく軽快に進むライトコメディの体裁で、答えのない問いを軽やかにさばいていき、思わず感動できるようにもなっている。
たとえばパンフレットに寄稿されたコラムには、「すべてはハッピーには行きつかないまでも、いい方向へと状況は変えられ」ていき、「そのじんわりと温かい友愛が心地よい」3と書かれている。ネットの記事でもこのような感想は散見されるので、ある程度はこうした理解のもとで肯定的に受け止められているようだ。
けれども、ホロコーストを扱った映画で「じんわりと温かい友愛が心地よい」という感想が出てくるのは、倫理的に問題があるともされかねない。かつてジャック・リヴェットは、『カイエ・デュ・シネマ』誌に寄稿した有名な「卑劣さについて」という文章で、ホロコーストを「悲劇」として演出することだけに固執し、圧倒的な現実を覆い隠してしまった映画監督を痛烈に批判した。アウシュヴィッツの惨劇を世界に知らしめた『シンドラーのリスト』(1993)でさえ、ホロコーストという表象しえない出来事をメロドラマへと歪曲したとしてクロード・ランズマンらから糾弾された。
一方『サウルの息子』(2015)や『関心領域』(2023)はそのような表象不可能性の問題や、悲劇のスペクタクル化への批判を意識したと思われ、これらは絶賛されている。アイゼンバーグも『サウルの息子』と『関心領域』を評価しており、『リアル・ペイン』が偽善的なホロコースト映画になることをもっとも恐れていたと述べている4。
では、アイゼンバーグはホロコーストを取り扱うにあたって、どのようにアプローチしたのか。彼はあるとき「「ホロコースト・ツアー(昼食付き)」という「気が滅入るような思いがけない広告」をネットで見つけ」「自分の家族の歴史の恐怖を目の当たりにしながらも快適さを求めているような、嫌な感情が入り交じりながら」それを読み、作品の中心的なアイデアを思いついたという5。
「ランチ付きのホロコースト・ツアー」というのはまさに「痛みのエンターテインメント化」の皮肉すぎる例と言えるだろう。リヴェットの議論はホロコーストの記憶が不適切に消費されていくことを倫理的に批判するものでもあるが、わたしたちがそのような問題に対して真面目に向き合い考えることができているかと言われればそれは疑問だ。もしホロコースト記念博物館を訪れショックを受けたとしても、建物を出てしばらくすれば、おおよその人は次にどこに行くか、食事は何にするかなどについて思い巡らすことだろう。それを責めても仕方がないし、それを咎められるほど「正しく傷つく」ことができる人はさほど多くはあるまい。
だからこそ批判が必要というのも理解できるが、『リアル・ペイン』はそうした問題から離れ、「痛み」の消費が求められる時代に、痛みのリアリティのありかを探っていくように企図されている。それでいて「正しく」傷つくことを強いるのではなく、「心地よく」傷つくことができるように調整されている。
それを確認するためにまずはあらすじを紹介していきたいが、最後まで詳細に追っていくため、未見であればまず作品をご覧になることを勧めたい。『リアル・ペイン』はここ10年のあいだでももっとも素晴らしい映画のひとつだと思っているからだ。
ご覧になっただろうか。では、前置きが長くなったが、始めていきたい。
祖母のルーツをたどる旅
ジョン・F・ケネディ国際空港のロビーにベンジーという男が座っている。年齢は40歳前後、表情は固く、やや緊張しているようにも見える。そこにいとこのデヴィッドがやってくる。ベンジーの態度は一変し、上機嫌で彼を迎える。彼らの祖母ドリーが亡くなり、ベンジーが落ち込んでいるので、立ち直るきっかけになればとデイヴが気を利かし、ドリーの祖国ポーランドのホロコースト・ツアーに申し込んだのだ。
祖母はホロコーストを逃れてアメリカに渡ったサバイバーだった。ツアー3日目に2人だけ離脱し、かつて祖母が住んでいた家を訪れてから帰国するというのがデイヴの立てた計画だ。
明示されてはいないが、デイヴもベンジーもおそらくユダヤ教徒ではなく、ユダヤ人であることに必要以上にこだわってもいない。そういう意味では今回のツアーは普段顧みることのない、ユダヤ人としてのルーツを振り返るものでもあった。けれどもベンジーはデイヴが立てた計画にあまり関心がないようで、こっそりマリファナを持ち込んで愉しもうとするなど、どこか気もそぞろだ。

© 2024 SEARCHLIGHT PICTURES
いとこ同士と言っても2人の性格は好対照だ。ベンジーは自由奔放で、空気を読まず言いたいことを言うタイプ。不興を買うこともあるが主張の内容自体はもっともで、また人を惹きつける魅力もあり、しまいにはみな彼を許してしまう。定職にはついておらず、家族や恋人もなく、ニューヨーク中心部からやや離れたビンガムトンで気ままな生活を続けている。
デヴィッドは礼儀正しく生真面目で現実的な人物で、ニューヨーク市内のアパートに住み、ウェブ広告の会社で働いている。やや神経質な一面もあるが、それは強迫性障害に悩んでいるからでもあるようだ。だが投薬治療により現在は安定していて、妻と小さい娘を大事にする、子煩悩な父親としての生活を大事にしている。
子供のころから強迫性障害に苦しんでいたデイヴに手を差し伸べ、助けてくれたベンジーに、デイヴは感謝している。当時のベンジーは輝いていて、疎遠になった今でも彼はデイヴの憧れの対象だ。気ままなベンジーに振り回されるのは悩みの種でもあるが、デイヴは彼を見捨てることはできない。
ワルシャワに到着した2人はホテルにチェックインし、ツアーメンバーと合流する。あいかわらず空気を読まないベンジーにデイヴは不安を抱くが、裏表なく人と接し、ツアーを楽しもうとするベンジーに周囲も打ち解け、難なく初日を乗り切る。
2日目。一行は列車に乗り込み、1等車でポーランド南東部の古都ルブリンへ向かう。だが、かつてユダヤ人が強制収容所へ「輸送」された過程を豪華な1等車で追体験するという皮肉な状況に耐えられないベンジーは周囲と揉め、車両から立ち去ってしまう。
デイヴはベンジーを追いかけ、なんとか2人で一行に追いついて合流し、旧ユダヤ人街を訪れる。ツアーメンバーと様々な悲劇について語り合うベンジーに、デイヴは水を差す。
でもすべての悲劇に涙してどうなる?
分かるけど悲しむには時と場所がある6
列車の中で揉めごとを起こしたベンジーへの苦言の意味もあるのだろう。しかしベンジーは「ホロコースト・ツアーだぞ」「今が悲しむべき時と場所でないなら──話にならない」と軽くいなす。
デイヴの迂遠な注意もむなしく、再び小さな波乱が起きる。旧ユダヤ人墓地でいつも通り解説を始めた英国人ガイドのジェームズに、またしてもベンジーが嚙みついたのだ。死者が眠る厳粛な場所なのだから、ここにいるあいだくらいは言葉を慎むべきだと彼は主張する。ジェームズは解説を控え、その代わり各自墓石の上に小石を置き、追悼の念を表すことにする。

© 2024 SEARCHLIGHT PICTURES
ディナーの席でもベンジーは気ままに振る舞い、場はシラけてしまう。ベンジーが中座すると、デイヴは酔いが回ったのか、彼への複雑な思いを吐露する。
あいつと一緒にいると時々疲れ果ててしまう
彼が好きだけど
すごく憎くて
殺したくなることも
でもあいつになりたい
一緒にいると……
自分がバカみたいだ
彼はクールで周りを気にしないから
ここに彼といると僕はすごく困惑する
理解できないんだ
この地の生存者からあいつが生まれたなんて
〔…〕
僕らの祖母も
根絶という恐怖から──
奇跡の導きで生き延びた
だからあいつを見ると聞いてみたくなるんだ
聞きたいけどどうしても聞けない
幾重もの奇跡を経て今存在してるのに──
なぜ睡眠薬を過剰摂取した?
最愛の祖母を失ったベンジーは、半年前に自殺未遂を起こしていた。デイヴの思いはこうだ。祖母を慕っていたのならばその思いを引き継ぎ、サバイバー3世として生き続けるよう努力すべきなのではないのか。周りを引っかき回すようなことは控え、安定した職につき、しっかりとした人間関係を築いて、自殺しようなんて考えずに生きられないのか。祖母は必死の思いで生き延びたのに、なぜその子孫がいいかげんな人生を送り、祖母が与えてくれた貴重な命を断つような真似ができるのか。そうベンジーに言いたくても言うことのできないデイヴに、みな同情する。
3日目。一行はツアーの山場とも言えるマイダネク──ナチスの絶滅収容所──へ向かう。ガス室や焼却炉を目の当たりにした彼らは押し黙り、帰りの車中、ベンジーのすすり泣く声だけが響く。

© 2024 SEARCHLIGHT PICTURES
ホテルに戻り、デイヴとベンジーはツアーから離脱する。ベンジーに魅了されたツアーメンバーは彼との別れを惜しむ。祖母が住んでいた街へ移動する途中、2人はビルの屋上へ忍び込み、マリファナをくゆらせながら会話する。デイヴはベンジーに帰国後どうするのかと問うが、その日暮らしの生活に先の展望はなさそうだ。一方、ベンジーはどうしてデイヴがビンガムトンまで訪ねに来ないのかと責めるも、家族と仕事で手一杯だとデイヴは言い訳する。興奮したデイヴはついに、なぜ自殺しようとしたのかとベンジーを詰問するが、答えは返ってこない。
翌日。2人はルブリンから50キロほど離れたクラスニスタウにある祖母の家へたどり着く。ベンジーは祖母に一度だけ叩かれたという話を始める。
夕食の約束に遅れたんだ
15分くらい
ハイだったし
マレーヒル地区の“ハドソン”で
──痛かった?
ものすごく
最高の出来事だよ
その後──
24時間至福が続いた
──ほんと? なぜ?
さあね
おばあちゃんは常連で客はみんな知り合い
でもおばあちゃんは正装して行く
客にどう思われようと俺を気にかけてくれた
だからうれしかったんだ
デイヴは、ツアー2日目に墓地でそうしたように、祖母の家の玄関先に小石を置くことを提案する。ベンジーも賛成するが、隣人からその家に住んでいる老人が躓いて怪我をするかもしれないと注意される。2人は小石を置くことを諦め、ポケットにしまい、帰国の途へ着く。
ふたたびジョン・F・ケネディ国際空港。デイヴはベンジーを自宅へ招こうとするが、空港で人間観察をするのが好きなのでしばらく空港にいたいと断られる。すると、デイヴは突然ベンジーの頰を平手打ちする。怒り出すベンジーにデイヴは、祖母のときは至福だったというから元気づけようとしたのだと弁解する。その気持ちを汲んだベンジーの機嫌は直り、デイヴを抱きしめて「おれは大丈夫」「心配するな」と告げる。
デイヴは自宅のアパートへ戻る。祖母の家で拾った小石を玄関先へ丁重に置き、部屋に入って彼の帰宅を待っていた妻子を抱きしめる。一方、ベンジーは空港のベンチに座り、ぼんやりと周囲を眺めている。落ち着きがなく不安げな表情で、のんきに人間観察をしているようではない。目は焦点を結ばず、うっすらと涙を浮かべているようだ。映画は終わる。
縦の痛み、横の痛み
Real Painという言葉には「うんざりするヤツ」という意味があるらしい。ベンジーはまさに「うんざりするヤツ」だが、けれどもこのタイトルからは、やはり「本当の痛み」という意味を重視すべきだろう。
この映画には複数の痛みが登場する。強迫性障害を患ったデイヴの苦痛。祖母を失ったベンジーの懊悩。自殺未遂をしたベンジーが昏睡する姿を思い浮かべるデイヴの心痛。これらは抽象的な痛みと言えるだろう。一方、ベンジーが祖母に叩かれたときの痛みに、デイヴが空港でベンジーをはたいた際の痛み、これらは現実的な痛みだ。そしてベンジーの自殺未遂という死へと誘う痛みに、映画全体を覆うホロコーストの、人類史レベルの巨大な痛み。
これら様々な種類の痛みを整理するために、「横」のデイヴと「縦」のベンジーに振り分けてみたい。
デイヴは周囲に気を遣える男だ。ベンジーを心配してわざわざツアーを計画してくれたし、ベンジーが状況をかき回せばフォローに努め、マイダネクで彼がショックを受ければ心配そうに見守る。強迫性障害を患っているのも、周囲の痛みに敏感すぎるがゆえかもしれない。
一方、ベンジーは空気など読まない。自分が正しいと思ったら率直にそう言うし、それで他人が不愉快になろうと気にしない。けれどもホロコーストの「痛み」に関しては敏感で、1等車でホロコーストツアーに向かうのは無神経だと訴え、墓地では神妙にすべきと説く。マイダネクではツアーの全員がショックを受けただろうが、嗚咽するほど取り乱したのはベンジーだけだ。

© 2024 SEARCHLIGHT PICTURES
デイヴはすすり泣くベンジーを気にかけるが、逆に言えば、彼にはベンジーを心配するだけの余裕があった、気持ちの切り替えができていたとも取れる。「すべての悲劇に涙してどうなる?」という割り切った思考の持ち主だ。このようにデイヴは「横」の痛みに敏感だが「縦」の痛みには鈍感な人物、逆にベンジーは「縦」の痛みには敏感だが「横」の痛みには鈍感な人物として描き分けられている。
こう整理したところでさらに注目したいのは、ベンジーの祖母が彼を叩いたときの「至福の痛み」だ。「24時間至福の時間が続いた」というのはいくらなんでも大げさだろう。ベンジーが祖母からの「痛み」をそこまで特別に感じているのは、この痛みが「横」軸と「縦」軸が交差する場所に突き刺さっているからである。
痛みの継承、あるいは愛
アイゼンバーグの亡くなった大叔母ドリスもユダヤ系ポーランド人で、第2次世界大戦前にアメリカに渡ってきたという。また彼はデイヴと同じように子供のころから不安障害を抱えていて、『リアル・ペイン』にはそうした監督自身の背景が投影されているようだ。ユダヤの伝統にもユダヤ教にも興味がなかったが、次第に自己のルーツであるポーランドに興味を持ち、何度も同地を旅して、今年ポーランドの国籍を取得するにまで至った。
祖母ドリーが住んでいた家を訪問するという設定も、アイゼンバーグ自身の体験に基づいている。大叔母の家を目の前にして何か強い感情に駆られるかと思っていたが、実際にはまったく感じられず、その経験が『リアル・ペイン』に発展したと述べている。映画の中でデイヴはこのように言う。
祖母のドリーを毎週木曜に訪ねてたんだ
すばらしい女性だった
今は見ない 古いタイプの現実主義者で
ぶっきらぼうでタフだったし
子供の頃はとても怖かった
この言葉にベンジーはすぐさま「怖いもんか」と否定し、「とても厳しく、唯一俺を素直にさせてくれる人だった」「他の家族は俺を見捨てたけど」と続ける。アイゼンバーグは2人の祖母ドリーについてこう述べる。
この映画の登場人物は祖母を恋しく思っていて、とりわけベンジーはその死を深く悲しんでいる。家族の中で彼を正してくれる唯一の存在だったからだ。けれども彼女は聖人ではない。だからこそリアルで、心に響くのだろう。真に過酷な状況を経験した人間は理不尽なほど自分を強くしなければならないので、小さな子供にとって恐ろしい存在になることがある。つまりベンジーが唯一愛を感じられる人は、彼にもっとも厳しく接した人物ということになるんだ。
〔…〕
もしあなたの祖父母が、歴史に残るようなとんでもなく耐え難い経験をしたとしたら、彼らはあなたの両親にとってストレスの多い親だっただろうし、あなたの両親もあなたにとってストレスの多い親となっただろう。7
ドリーがどういった人物だったか、デイヴとベンジーの言葉から読み取れることは少ない。断片的な情報からは、自分にも他人にも、かわいいはずの孫にも厳格で、身内にも弱みを見せるようなタイプではなかったと推察できる。そしておそらく彼女は、ホロコーストの体験を子供や孫に伝えるようなこともしなかったはずだ。

wikimedia commons
デイヴにとって祖母は畏怖の対象だった。けれどもベンジーにとっては真逆で、唯一彼に優しく接してくれる人だった。ではドリーはベンジーだけをかわいがってデイヴには厳しく接していたのだろうか。そうではないだろう。ドリーは同じように孫たちを扱っていたが、2人が違う受け取り方をしたのだ。ではドリーから受ける印象がデイヴとベンジーでここまで異なるのはなぜか。デイヴは強迫性障害を抱えていたようだから、そのせいで必要以上に祖母を恐ろしく感じていたのかもしれない。けれどももうひとつ、2人には相違点がある。
ベンジーは、祖母以外の家族は自分を見捨てたと言う。デイヴが両親について語るシーンはないが、言及しないということはベンジーの家族ほど悪い関係ではなかったのだろう。そうすると、デイヴは優しい両親のもとで育っていたため祖母の厳格さに慣れることができず、子供らしく怖がったというところではないだろうか。一方ベンジーは、本来両親から与えられるはずの愛情をドリーに求めていた。そうした家族関係の違いが、祖母の印象を変えていったのだろう。
けれどもドリーはホロコーストの記憶を押し殺すため、ベンジーにも「ストレスの多い」祖母として接していたはずだ。ベンジーが叩かれたエピソードもそれを物語っている。ベンジーは喜んでいるが、「ものすごく痛かった」というくらいだし、厳しく見れば不当な体罰と言えなくもない。英文学者の坂野明子はこのように論じる。
あまりにも過酷な体験をしたサバイバーは、たとえ相手が血を分けた子供であっても、いやおそらく子供であるからこそ、自身の体験を進んで語ろうとせず、結果として、親と子の間に目に見えぬ壁ができてしまう。壁にはじかれた子供は親の愛が育む自己肯定感を得られず、大人になっても精神的に不安定なままであり、同時に、ホロコーストにまつわる「疑似記憶」に苦しめられもする。8
サバイバーの沈黙は、家族や子供に余計な心配をさせたくない、不安にさせたくないという気遣いや優しさに起因するものでもある。けれども子供からすればそれは別種の「痛み」を誘発し、ときには精神的な暴力となって、かえって彼らを苦しめることとなる。圧倒的な悲劇から家族を守ろうとする努力が、皮肉にも別のかたちで負の連鎖を招いてしまうのである。
さてベンジーはと言えば、ホロコーストの恐怖に起因する祖母の厳格さを愛情だと受け取っていると、ひとまずはそう見ることができる。叩かれたことをDVではなく「至福」と感じたのも、その「痛み」を祖母の優しさと解釈したからだ。ホロコーストの圧倒的な「痛み」が、祖母に叩かれた「痛み」を通して自分に継承された、そしてその「痛み」こそ彼女が自分を愛してくれた証しなのだと。
このように祖母の体罰は、ベンジーにとって祖母とのつながりを刻む「横の痛み」であると同時に、ホロコーストの記憶をかすかに伝える「縦の痛み」でもあるのだ。
死者の側の人間
しかし、そうするとベンジーは、ねじれたかたちで「痛み」を継承しているきらいがある。アイゼンバーグは、もし亡くなった彼の大叔母が『リアル・ペイン』を見たとしたらなんと言ったと思うかと問われ、こう答えている。
きっと大叔母は、偉大な実存的探求のふりをした自慰的な創作にわたしが耽っていると言うだろう。それはきっとその通りだ。でも彼女はポーランドで育ち、ポーランドとのつながりを深く感じることができた。だから、わたしやわたしの世代にとってはそういった経験なしに育つこともまた別の苦痛なんだけど、彼女にはそういうことは理解できないと思うんだよね。9
アイゼンバーグが言うような「深いつながりを感じられないことによる痛み」は、ホロコーストの「痛み」と比べればたいしたことはない。けれどもアイゼンバーグやその世代にとっては、その喪失感もたしかな「痛み」だ。
クローネンバーグが『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』で描いたように、たとえ人類が痛みを排除できたとしても、人は痛みを求めることだろう。痛みもまた、その人を構成するのに欠かせない要素なのだから。
デイヴはユダヤ教徒ではなさそうだし、ユダヤ人であることをアイデンティティの基盤にするようなタイプでもない。けれども彼が「ベンジーみたいになりたい」と言うのは、ベンジーがホロコーストの犠牲者の思いを共有できる、「縦」のつながりの中にいるからでもあるだろう。

© 2024 SEARCHLIGHT PICTURES
ではそのベンジーが自殺しようとしたのはどうしてだろう。祖母を通してユダヤの世界に迎えられたと感じているのなら、彼女が世を去っても、そのつながりをもとに生きていけないものなのか。祖母の死はそれを上回る衝撃で、彼女のいない世界に絶望したのだろうか。
それだけではないように思える。アイゼンバーグは興味深いエピソードを紹介している。
デヴィッドとベンジーがポーランド最古の墓地で墓石を眺めるシーンがある。ベンジーはガイドのジェームズに、ここは地下に眠る人々について考えるべき場所であって、たんに歴史や日付を語るところじゃない、アカデミックすぎる、と怒り出す。実はこの場面、脚本を書いているときは、自分が何を書こうとしているのかわかってなかったんだ。ところが母が初期の編集版を見て、そのシーンで泣いたと教えてくれた。なぜかと聞いたら、ベンジーは本当に死にたがっていたからだと、そう言うんだよね。10
ベンジーは自らも死者の側の人間だと思っているから、ガイドの態度に腹を立てたと言うのだ。アイゼンバーグは母親の解釈に妥当性を認めているし、たしかにベンジーの内面を言い当てているように感じる。
ベンジーは祖母の体罰を「至福の痛み」としてポジティブに受け取った。「至福」という言葉、実際にはカルキンは「literally elated(文字通り舞い上がった)」と言っていて、これが宗教的な言い回しなのかはわからないが、それを「至福」と表現するのは的確のように思える。このときベンジーを貫いた痛みは、彼にとって宗教的な体験のはずだからだ。
医学博士の外須美夫は、キリスト教における「痛み」は「主のなし給う御手であり」「そして神の愛でもあった」11と述べている。ベンジーも信仰心こそないだろうが、彼は彼で「深いつながりを感じられないことによる痛み」に苦しんでいたのだろう。そうしたところに祖母の体罰によって「神の愛」を感じ取り、救われたと思ったのではないか。この映画の宗教性について、あるインタビュー記事では次のように指摘されている。
2人は〔ユダヤの教えに従って〕毎週安息日に家にこもったり、毎日戒律通りに行動したりするのにいまも抵抗を感じている。けれど、宗教に対するこうした不安こそが、この映画をよりユダヤ的なものにしている要因のひとつでもある。なぜなら、そのような信仰体系がこんにちどのように生き残ることができるのか、そういった真実をこの作品が描いているからだ。12
ここでは「ユダヤ的なもの」と言われているが、熱心な信仰者ではなくてもいざというときは思わず神に祈ってしまうというのはよくある話だ。デイヴもベンジーも信仰心はないとはいえ、それぞれに不安を抱える2人は、心のどこかで超越的な何かを求めていたのだろう。デイヴは結局それを見つけられなかったが、かわりに家庭を築くことで生きるための拠り所を得ることができた。孤独なベンジーはそうした存在を手にすることはできなかったが、祖母との「痛み」を通じたつながりによって、なんとかここまで生き延びてきた。
けれどもその痛みは、祖母が家族に知ってほしくなかった、ホロコーストの死の記憶の残響でもある。ベンジーがその痛みに愛を感じたということは、死に魅了されていたとも取れる。
祖母が世を去った今、ベンジーは死の痛みだけが祖母の愛、先祖の世界につながるよすがだと感じている。それこそが彼を自殺に誘った要因だったのではないか。そしてもはや、デイヴが祖母のようにベンジーを叩打しても、彼を現実社会に引き戻すことはできないのだ。
孤独という煉獄の底で
ベンジーは孤独だ。家族との関係はよくなく、親しかったはずのデイヴも訪ねてくることはない。遊び友達はたくさんいるだろうが、デイヴのように心から付き合える親友や恋人はいなかったに違いない。ベンジーを現世につなぎ留めてくれるのは、あとは祖母だけだった。
けれども祖母は死んだ。ツアーを通してデイヴとの友情も復活したかに思えたが、彼は自分の生活を犠牲にしてまでベンジーとの交友を再開させようとはしない。映画のラストに関して、アイゼンバーグはこう答えている。
空港でのエンディングシーンに温かみを感じるかもしれないけど、ベンジーがデヴィッドの家を訪れることはないし、ベンジーは基本的にデヴィッドが望むような人間にはなれないだろう。だからこの映画のエンディングでは、デヴィッドが家族との安定した生活に戻っていくシーンと、煉獄にとどまり続けるベンジーのシーンとを交互にモンタージュしているんだ。13
『リアル・ペイン』はオープニングもエンディングも、ベンジーが不安げな面持ちでひとりたたずむシーンとなっている。これはデイヴとの旅を経てもなおベンジーが変わることなく、孤独なままであることを雄弁に物語っている。


© 2024 SEARCHLIGHT PICTURES
別れ際にベンジーは「おれは大丈夫」と言う。デイヴはその言葉を信じたようだが、その判断は誤っている。ベンジーが祖母を大事にしていたのは間違いないが、今彼が何より求めているのは、デイヴとの友情の復活だったのだから。
けれどもデイヴはベンジーと、子供のころのような親密な付き合いをふたたび始めようとは望んでいない。トラブルメーカーのベンジーとの交友の再開は、家族を犠牲にすることを意味する。それを悟ったベンジーは、デイヴが自宅に招こうとしても、あえて応じなかったのだ。
デイヴは不義理な人間だろうか。そうかもしれないが、けれども現実はそんなものだ。手のかかる友人や恋人、家族や親戚と付き合いきれなくなり縁を切ったという経験は、多かれ少なかれ誰にもあるはずだ。
それを責める気はないし、デイヴがことさら薄情で冷たい人間だとも思わない。人にはそれぞれキャパシティがある。どんな過酷な状況だろうと他人に尽くすことのできるオスカー・シンドラーのような偉人もいれば、自分ひとりが生きていく、それだけで限界という人もいる。とりわけ精神的な病を抱えるデイヴのような男は、妻子のために毎日仕事に励むだけで精一杯だろう。
けれどもベンジーのことを考えると納得できないというのもわかる。率直に言ってわたしは、ベンジーは「煉獄」を生き続けることに耐えられず、このあとふたたび最悪の決断を下すだろうと思っている。そしてそれは、ベンジーが再度死地に向かっていくのを、デイヴが許してしまったことを意味する。
欺瞞を抱えて生きる
祖母の旧宅で拾った小石を、デイヴは自宅の玄関先に置いた。ユダヤ文化には墓参りの際、死者への敬意を表すため墓石の上に石を置く習慣がある。『シンドラーのリスト』で、シンドラーの助力によりナチスの手から逃げ延びたユダヤ人とその子孫が、彼の墓に石を置いていくエンディングを覚えている人もいるだろう。

© 1993 Universal City Studios, Inc. and Amblin Entertainment, Inc.
一方、ベンジーが石をどうしたかは描かれない。デイヴ以上に義理堅いベンジーのことだから、その辺に放り出すようなことはなく、空港においても石を所持し続けているはずだ。けれどもそれは、ベンジーが死を抱えたままということでもある。
そうすると小石を玄関先に置いたデイヴは、死を家の中に持ち込みたくないと無意識のうちに考えたとも言える。割り切りがよく現実的な、彼らしい思考だ。デイヴは気のいい男だが、ベンジーに対しても祖母に対しても、どこかで一線を引いているところがある。それでも彼が薄情な人間だとは言えまい。
見方を変えてみよう。あえて言及しないできたが、これだけユダヤ性を中心に据えた映画を今見るとなると、誰しもイスラエルのガザ侵攻が脳裏をかすめることだろう。映画にはガザで起きていることがまったく反映されていないという意見もあるようだが、『リアル・ペイン』の撮影は2023年の5月から6月にかけて、ガザ侵攻のきっかけとなったレイム音楽祭虐殺事件はその年の10月に起きたため、それを作品に求めるのは筋違いだ。ただわたしが観測している限りでは、アイゼンバーグは今回のガザ侵攻について何もコメントしていない。しかしこれに関しても、ユダヤ人コミュニティに身を置く関係上、公然と口にしにくいのも予想できることで、虐殺を支持しているわけではないだろう。
ホロコーストの悲劇がガザで繰り返されていることは無視できない。けれども、遠く離れた場所で声を上げ、募金をし、関連企業の不買運動を行ったとしても、国家レベルの暴力を食い止めるのは難しい。できるかぎりの支援はしつつも、デイヴの言う通り「悲しむには時と場所がある」とどこかで割り切るしかない。「すべての悲劇に涙」していては自分の身を滅ぼしかねない。なにしろ、ベンジーはそういう人間だったのだ。
『リアル・ペイン』がホロコーストを扱っていながら「心地よい」映画だという理由は、この点にある。デイヴはベンジーに手を差し伸べておきながら、肝心なところでそれを引っ込める、欺瞞的な人間だ。けれどもベンジーはデイヴの不義理を呑み込み、空港に残ることを選択する。それを「じんわりと温かい友愛が心地よい」と受け取ってしまうのは、わたしたちもまたデイヴ側の人間だからだ。自分が偽善的で欺瞞に満ちた人間だと直視するのを避けたいがため、「心地よい友愛の映画」と受け取らなければやっていけないのだ。

© 2024 SEARCHLIGHT PICTURES
ベンジーがふたたび自殺を試みたとき、デイヴは強い痛みに苦しむことだろう。そして空港での別れを思い出し、あのとき家に誘ったのに断ったのはベンジーだった、彼は「おれは大丈夫」と言っていたのだと反芻するだろう。その言葉はベンジーの優しさから発されたものだが、その裏に貼り付いた絶望的な諦念を感じ取って、その気遣いになおさらデイヴは後悔の念に駆られるだろう。『呪術廻戦』の登場人物のように、ベンジーの死はデイヴにとって、呪いとなって降りかかるだろう。
けれどもベンジーは、自分を救ってくれなかったデイヴを許す。デイヴが側にいなければ耐えられないならそう言えばいいのだし、空港でのやけに割り切りのいい別れは、常に周囲を振り回してきた彼らしくないものだ。しかしベンジーは、デイヴが今生きていられるのは妻子の存在あってこそで、自身の居場所はもうデイヴの世界にはないことを悟り、自分の介入でそれが乱されるくらいなら身を引くことを選ぶ。いつだって自分勝手なベンジーだったが、病に苦しむデイヴの人生を尊重し、ひとりでいることを選択したのだ。
それを察したデイヴの心をかすめる痛みは、罪悪感へとかたちを変え、彼を責め立てるに違いない。そしてそれは、わたしたちが世界の悲劇から目を逸らすことで覚える心の痛みに似ている。
だが『リアル・ペイン』はその痛みを包み込む。観客は心の痛みを「じんわりとした心地よさ」だと防衛的に誤変換し、本当の感情に蓋をしたまま、映画館を後にするだろう。これこそ「痛みの時代」にふさわしい、「不幸をエンタメとして楽しむ」ための理想的な作品ではないだろうか。
このように痛みを感じることは、「正しい傷つきかた」と言えるだろうか。痛みを「心地よく」消費することは、間違った傷つきかたなのだろうか。
今のようにいつでも「正しさ」が求められる時代には、このような欺瞞的な痛みは正しくないのかもしれない。けれども『リアル・ペイン』は、痛みを「ランチ」のように消費することも、小さな救済なのだと語りかけてくる。その痛みは「本当の痛み」ではないかもしれないが、「間違った痛み」でもないはずだ。欺瞞に満ちた「痛み」を抱え続けることによって、わたしたちはこの煉獄を、絶望にからめとられずに歩いていけるのだから。
著者
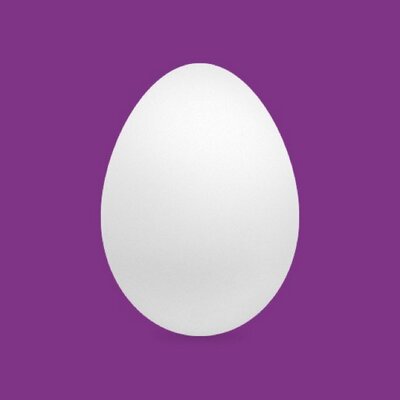
noirse
低志会会員。佐々木友輔氏との共著『人間から遠く離れて──ザック・スナイダーと21世紀映画の旅』(トポフィル、2017)発売中。
連載:小人閑居為不善 日記(Mercure des Arts)
\ ご支援よろしくお願いします! /
関連記事
関連商品
脚註
- 戸部マミヤ「「ちいかわ」はなぜ読者を狂わせるのか? 助けてください、僕らはふわふわの綿あめで首を絞められています」、ねとらぼ、2020年12月19日。 ↩︎
- 以下、海外サイトからの引用はすべてnoirseの訳による。Terry Gross, “In ‘A Real Pain,’ Jesse Eisenberg asks: What is the purpose of ‘tragedy tourism’?” NCPR, 21 January, 2025. ↩︎
- 金澤誠「ユニークな歴史観が目を引く、対照的な二人のロードムービー」、『リアル・ペイン~心の旅~』公式パンフレット、2025年、19頁。強調は引用者。 ↩︎
- Catherine Shoard, “‘Every day is 24 hours of panic to just get out the door’: Jesse Eisenberg on self-indulgence, candid aunts and his Oscar-tipped Holocaust comedy,” Guardian, 10 January, 2025. ↩︎
- 「『リアル・ペイン』の背景」、『リアル・ペイン~心の旅~』公式パンフレット、2025年、35頁。 ↩︎
- 引用するセリフはすべて『リアル・ペイン』(字幕翻訳・松浦美奈)に則る。 ↩︎
- Darren Richman, “Jesse Eisenberg: ‘Is our modern pain valid?’” Little White Lies, 13 January, 2025. ↩︎
- 坂野明子「記憶に手を届かせるために──次世代の模索」、『ホロコースト表象の新しい潮流:ユダヤ系アメリカ文学と映画をめぐって』所収、彩流社、2018年、60頁。 ↩︎
- Shoard, “‘Every day is 24 hours of panic to just get out the door’: Jesse Eisenberg on self-indulgence, candid aunts and his Oscar-tipped Holocaust comedy.” ↩︎
- Destiny Jackson, “Jesse Eisenberg Opens Up About ‘A Real Pain’,” Deadline, 12 December, 2024. ↩︎
- 外須美夫『痛みの声を聴け 文化や文学のなかの痛みを通して考える』、克誠堂出版、2005年、59頁。 ↩︎
- Ella Kemp “Friendship Lessons: Jesse Eisenberg and Kieran Culkin share five things A Real Pain taught them about each other,” Letterboxd, 8 January, 2025. 強調は原文。 ↩︎
- Jackson, “Jesse Eisenberg Opens Up About ‘A Real Pain’.” ↩︎