日本のオタク文化が海外でも人気を博すようになって久しい。だが、国境を越えた「トランスナショナル」な文化実践の豊穣さは、大資本が主導する「正史」からは見えなくなってしまう。その象徴とも言える例が、2000年代日本の文芸誌『ファウスト』の中国における“創造的誤読”だ。大陸や香港、台湾において「ファウスト的なもの」はいかに受容されたのか。評論同人誌『東アジアのなかでの「ファウスト系」』(2025)より、中国出身の批評家・紅茶泡海苔(コウチャアワノリ)による巻頭言「ファウスト、あるいはオタクカルチャーのトランスナショナルティ」を改題してお届けする。
文:紅茶泡海苔
編集協力:舞風つむじ
オタクカルチャーのグローバル化
2020年代──それはオタクカルチャーのグローバル化が新たな波として、その存在感を示す時代である。『アズールレーン』(2017)を皮切りに、『原神』(2020)、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』(2021)、『勝利の女神:NIKKE』(2022)など、中韓発のソーシャルゲームがインターネットを介して世界的にヒットしただけでなく、従来の文芸領域にも新たな動きが見られた。
劉慈欣『三体』(2008)の世界的好評を発端に、今までローカルだった中国語小説は海を越え、日本でも広く読まれることになった。華文ミステリー・SF・百合の「三銃士」はその代表格といえるジャンルであり、今や日本の文芸シーンにおいて独自の読者層を開拓している。

出典:ブルーアーカイブ The Animation 公式サイト
©Nexon Games/アビドス商店街
コンテンツ産業を主導する大資本間の提携もまた、この時代の特徴を強く示している。日本のオタクカルチャーの一角を占める美少女ゲームブランド「Key」を擁するビジュアルアーツが中国資本であるテンセント・ホールディングスに買収され、そのテンセントがKADOKAWAに追加投資し、さらなる資本提携を図ることで、オタクコンテンツのグローバル展開に拍車をかけていく。『ナルキッソス』(2005)のように若干実験的に見えるノベルゲームですら、今や中国で映画が制作されるまでになった。
Xでよく揶揄される話題として、中国が『原神』、韓国が『ブルーアーカイブ』、日本は「野獣先輩」をお互いに輸出することで新時代の「三角貿易」が成り立っているというネットミームがあるが、これはオタクカルチャーの「大航海時代」、言い換えれば、そのグローバル化が非常に顕著であることを、無意識のうちに言い表していると思う。「三角貿易」という言葉そのものが孕むネガティブな意味合いも含めて、である。
東アジアにおけるオタクカルチャーの一体化が、それを享受するオタクたちにとって胸が躍る事態であることは事実だが、しかし同時に、どこか複雑な気持ちも抱いてしまう。それは、プラットフォーム大資本によるグローバル戦略に、自分たちが築き上げて来た文化が望ましくない形で利用され、取り残されていく未来を、皆うっすらと想像しているからだ。
KADOKAWA的なもの vs. ファウスト的なもの
2021年に出版された『KADOKAWAのメディアミックス全史 サブカルチャーの創造と発展』は、このようなオタクカルチャーがグローバル化する流れを、「正史」として記述しようとする書物である。台湾角川から始まり、広州天聞角川動漫としての中国大陸への進出、さらにはアメリカに根付いたことや、アジア諸地域における「クールジャパン学校」の設立等々、オタクカルチャーのグローバル化が、クールジャパン政策と大手コンテンツ会社のグローバル戦略の成功を示す好例として語られている。

出典:KADOKAWAグループ ポータルサイト News Release
たしかに、大手コンテンツ会社と大資本によるグローバル戦略は、オタクカルチャーを享受するための流通経路、言い換えればアーキテクチャを構築したという意味において、ただならぬ貢献をしたと思う。しかし、そのグローバル化を受け止める「ローカル」の文脈もまた重要である。もちろん、KADOKAWAが展開するグローバル戦略にはローカルなものが欠落していた、というわけではない。そこには当然、現地の出版社や文化産業と交流する場面もあった。だがそれは、ローカルなカルチャーを再編し、そこに「指導」を行うようなものだった。台湾角川と広州天聞角川はまさにそうした「指導」の賜物である。
昨今のグローバルなオタクコンテンツを追っている読者ならば、上記の「KADOKAWA史観」に対して、本能的に疑問を感じ取るであろう。というのも、『原神』『ブルーアーカイブ』といった中韓発のオタクコンテンツは、KADOKAWA的なメディアミックス戦略を当然のように展開しているにもかかわらず、その内容には「KADOKAWA的なもの」がほとんど見られないからである。
例えば、KADOKAWA傘下の電撃文庫から出版されているライトノベル『ソードアート・オンライン』(2009)は、アジアだけでなく欧米でも絶大な人気を誇り、世界に通用するライトノベルの代表例といえる。だが、同じくライトノベルから多大な影響を受けている『原神』や『ブルーアーカイブ』は、それとはどこか根本的な違いがあることを、少なからぬユーザーはおそらく身をもって感じ取っているであろう。
その代わりに私たちは、次のようなキーワードをたびたび目撃する──それが「ファウスト系」である。『ブルーアーカイブ』のシナリオディレクターを務めたisakusanはインタビューのなかで、自身に多大な影響を与えた日本の作家として奈須きのこ、西尾維新、舞城王太郎などを挙げ1、また『原神』と同じく中国のmiHoYo(米哈遊)が開発する『崩壊:スターレイル』(2023)のプロデューサーを務めるDavid Jiangも、思春期に「TYPE-MOON」作品に触れたことがクリエイター活動の原点にあると告白し、奈須きのこと夢の対談を実現した2。
不思議なことに、皆自分が影響を受けた存在として同じクリエイターたちの名前を挙げているのだ。そしてそれらのクリエイターたちはまさに、ゼロ年代の日本において一世を風靡した文芸誌『ファウスト』の中心にいた人々なのである。
『ファウスト』は講談社所属(のちに星海社社長)の編集者・太田克史が2003年に創刊した文芸誌。当時主流のライトノベルとは一線を画す「新伝綺」を標榜し、2011年のVol.8で事実上休刊するまで、奈須きのこ、西尾維新、舞城王太郎のほか、佐藤友哉、滝本竜彦、上遠野浩平、竜騎士07、東浩紀、笠井潔など気鋭の作家・評論家が参加した。2006年には台湾の先端出版から『浮文誌』のタイトルで繁体字中国語版が刊行されている。また2008年のVol.7では中国特集が組まれ、後述する青春文学作家・郭敬明の小説やインタビューなどが掲載された。[編集部註]

出典:講談社ウェブサイト
だが、どちらかといえばKADOKAWAに類似した中国資本で活躍するクリエイターが、なぜゼロ年代日本の、それも比較的マイナーな文芸誌から出発した一連の文芸作品・運動にこれほどのリスペクトを示すのか。日本のオタクたちからすれば、それはわかるようでわからない、非常に奇妙な現象であろう。
しかし、私たち中国のオタクにはわかる。なぜ『ファウスト』に代表されるゼロ年代文芸の想像力が、KADOKAWAのようなグローバルな大資本、そしてオタクカルチャーの流通経路を支配するアーキテクチャを飛び越え、中韓ひいては東アジアに巨大な影響を与えてきたのか──。
本誌『東アジアのなかでの「ファウスト系」』では、今まさにリアルタイムで進行する上述の文化現象を直接的に論ずるわけではない。そうではなく、華文世界の経験から、そのような現象が生まれるまでの歴史的・地域的文脈、そしてその文脈において「ファウスト的なもの」が果たした役割をそれぞれの執筆者が振り返って記述し、この疑問を解く手助けになるであろうひとつの「視点」を提供すること──これこそが本誌の狙いである。

出典:紅茶泡海苔BOOTH
インターネット中心モデルの限界
先ほど、私たちはKADOKAWAがオタクカルチャーの指導者として居座り、東アジアにおける受容をあたかもクールジャパン政策の成果であるかのように語る書物の存在を確認した。KADOKAWA的なものが、このようなオタクカルチャーのグローバルな側面を代表するものだとすれば、本誌が紹介する華文世界の歴史と文脈は、そのヘゲモニーへの、一種のローカルな抵抗として捉えられるかもしれない。
華文世界における日本オタクカルチャーの受容について語る際、「インターネット」と「海賊版」の重要性はよく引き合いに出される。KADOKAWAに代表される大資本が正規の流通経路を築く前に、「字幕組」(ファンによる字幕の制作)やBBS(ネット掲示板)におけるコミュニケーション、そしてP2P形式のファイル共有ソフトなど、すでに水面下で非正規のネットワークが形成されていた。これらの実践は多くの研究や紹介のなかで、草の根的な受容運動として高く評価されてきた。
例えば、1990年代中盤に台湾で発祥した「ACG」(Anime・Manga・Game)3という言い方は、日本のオタクカルチャーを含意しつつも、独自の意味合い4を持った言葉としてよく言及される。たしかに、正規の流通が存在しなかった時代において、海賊版や字幕組、ネット掲示板を通じた消費と情報交換は重要な役割を果たした。
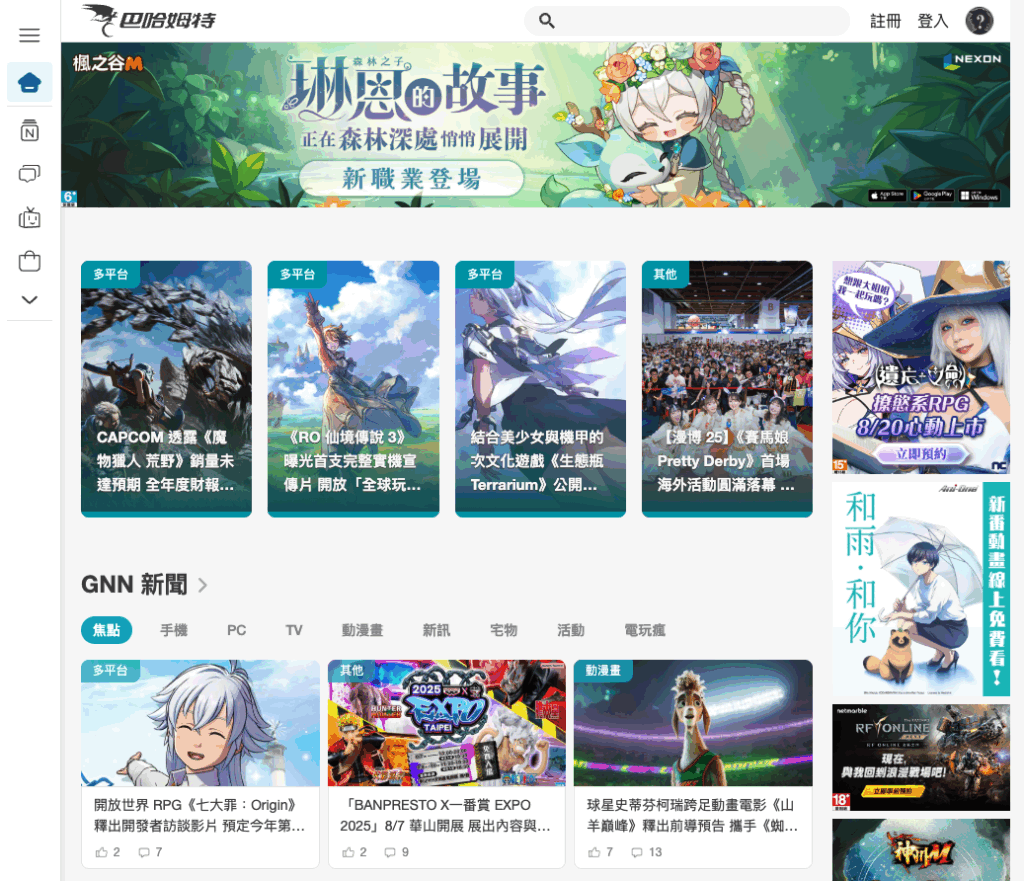
だが、このようなインターネット中心の受容モデルには、いくつかの見過ごせない限界がある。とりわけ、オタクカルチャーの受容を、メディア環境の変化によって一挙に説明しようとする点において、文化の地層的な重なりや、制度・歴史・政治といった複雑な文脈を見えにくくしてしまう。
1. 「断絶の欲望」の不可視化
インターネット中心の受容モデルの問題点としてまず挙げられるのは、インターネットという新たなメディアの登場が、既存の文化的・制度的な文脈を断ち切る「革新」として語られることで、それ以前に存在していた現地のファンコミュニティや文化的実践が忘却され、あたかも存在しなかったかのように扱われる危険性があることだ。
たしかに、インターネットを通じて新たなコミュニティが形成されたのは事実だが、その成立には、制度的制約、検閲、経済格差、出版政策など、多様な歴史的条件が絡んでいる。ところが、メディア環境の劇的な変化に目を奪われるあまり、その変化がもたらした「断絶」がどのように構造化・正当化されたのかは棚上げされてしまう。
特に見落とされがちなのは、その断絶がしばしばファンコミュニティ自身によって望まれ、積極的に構築されたという点である。前時代の制度や文化的権威から距離をとり、新たな物語、新たな美学、新たな連帯を求めた結果として日本のオタクカルチャーが選び取られたこと、それゆえそこには「断絶の欲望」が働いていたことに、改めて目を向ける必要がある。
2. 後ろめたさによる制度への回収
次に考えなければならないのは、上述した海賊版などの非制度的手段を通じて形成された受容の実践が、しばしばファンたちに複雑な感情を引き起こすということだ。
たしかに、制度外の方法で好きな作品にアクセスする行為には(目の前の制度からの)ある種の解放感が伴い、新たなコミュニティの形成を促す側面がある。しかし同時に、それが法的・制度的に「正しくない」ことをどこかで意識しており、そこにはかすかな罪悪感や、危うい立場への自覚が常につきまとう。このような後ろめたさは、やがて制度との折り合いをつけようとする形で、さまざまな「代償行為」へと向かう。
例えば、かつて非正規に入手した作品を正規流通の開始を機に再購入する行為(中国語でいうと「補票」)や、制度的正統性を帯びたプラットフォーム(出版社、配信サービスなど)の利用などを通じて、自己の実践に「正当性」を与えようとする動きがそれである。ここでは制度への回収がむしろファン側の内的要請として進行し、そしてこうしたプロセスのなかで、非制度的な実践は徐々に制度的な物語へと書き換えられていく。それは「正しさを取り戻す」ための自己物語化の一環であり、またその物語化の過程が「正史」──つまりKADOKAWAのグローバル戦略に基づく制度的成功譚──と接続しやすい構造を生む。
3. 多様な語りの抑圧
最後に議論する必要があるのは、インターネットというメディアが作り上げる共時的幻想が、文化の受容を均一なものとして描き出しやすいことである。
SNSや配信プラットフォームを通じて、特定のコンテンツに対する反応がリアルタイムで可視化される環境では、「今みんなが見ている」「みんなが同時に感じている」という感覚が生まれやすい。だがその背後には、通信環境やアクセス地域、言語的障壁といった要因によるタイムラグや受信格差が確実に存在している。
このような格差は、コンテンツや情報に対する「反応の早さ」を文化的参与の前提にし、その結果、遅れてアクセスする受信者の声は「周回遅れ」として退けられてしまいやすい。インターネットというメディアの構造そのものが、文化受容の多様性を抑圧し、主流の語りに吸収する装置となっているのである。
これらの問題点を踏まえると、「インターネット」というメディア的視点から語られる文化受容の物語が持つ、制度的で、技術決定論的な側面が見えてくる。その語り口は結局のところ、KADOKAWA的なものへと合流する宿命にあるのかもしれない。受容の情熱も、創作の欲望も、やがては「正史」の物語のなかに編み込まれていく。それは、資本の力によってそうなってしまうというだけではない。おそらく私たち自身が、制度に吸収されることをどこかで望んでしまっているからだ。
こうした「葛藤」を見つめ直すためにも、あえてインターネットから目を逸らす必要がある。メディアの変化を歴史の中心に据えることをやめ、その変化の周縁で繰り返されてきた断絶と持続の運動、見えにくい翻案と模索の軌跡に視線を向けなければならない。そこにこそ、「制度と付かず離れずの語り」を紡ぎ直すための余白がある。
グローバル、ローカル、トランスナショナル
先ほど私は、華文世界のオタクカルチャー受容の歴史と文脈は、KADOKAWAが主導するグローバルなヘゲモニーに対するローカルな抵抗であり得ると述べたが、上記の議論を経て、ようやく見えてくる別の地平がある。すなわち私たち自身が、制度に吸収されることをどこかで望んでしまっているということだ。
この欲望は、ローカルな実践がグローバルな物語へと統合される過程において、しばしば見過ごされている。しかし、そのような制度的枠組みへの接続の欲望と、制度に乗らない創作の衝動とのあいだにこそ、文化が生成されるアクチュアリティがある。「グローバル」と「ローカル」のどちらにも寄りきれない、あるいはどちらからも浮いてしまうような「中間」においてこそ、文化的欲望のねじれやズレがもっとも露呈する。
『ファウスト』的なものが華文世界において、この「中間」の場所にとどまり続けるためのシンボルになったのは、おそらく偶然ではない。それは、制度の外にあったからでも、単にマイナーだったからでもない。むしろ『ファウスト』が当初から持っていた編集方針の曖昧さや、文芸誌でありながらラノベ的なものでもあったというジャンル的な宙づり、そして何よりも、読者の側に「この雑誌は何かを変えてくれるかもしれない」という期待と誤解がないまぜになった想像力をかき立てたことが大きい。
『ファウスト』はひとつの「場」であり、「間」であった。その「場」ないし「間」の不安定さが、ファンたちの想像力をむしろ活性化させ、制度に回収されるのを避けるための猶予を与えた。だからこそ、ファウスト的なものはKADOKAWAのようなグローバルな軌道に乗ることなく、しかしローカルな内向にも閉じずに、東アジアのオタクカルチャーの深層に入り込むことができたのかもしれない。
それは一種のトランスナショナルな文化実践である。ここでいう「トランスナショナル」とは、単にコンテンツが国境を越えて流通し、冒頭で述べたような「三角貿易」になるという意味ではない。むしろ、制度的な承認や正規の流通に回収されながらも、そこからはみ出す形で独自の受容と抵抗が生じ、それらが互いに「響き合ってしまう」ような、いわば「誤配的」なものである。
本誌は、この中間的な実践を記録し、批評し、その輪郭を描き直す試みである。トランスナショナルとは、越境の事実そのものを指すのではなく、越境をめぐる関係性の形式であり、その実践のあり方なのだ。
本誌収録論考ダイジェスト
本誌『東アジアのなかでの「ファウスト系」』では、上述したトランスナショナルな視点から、華文世界のオタクカルチャーの受容、そこから派生する実践、そしてその文脈における「ファウスト系」の影響について各執筆者が振り返る。ここからは、各論考の内容を紹介する。
1. 中国大陸篇 〜変奏される『ファウスト』
本誌は「中国大陸篇」「香港篇」「台湾篇」の3部からなる。まず「中国大陸篇」では、2000年代中盤、中国青春小説の旗手・郭敬明と文芸誌『ファウスト』との偶発的接触から入り、そこから展開される中国大陸独自のライトノベル文芸運動の歴史的意義と功罪を再検討する。
このパートではまず、本誌の編集長である私、紅茶泡海苔による論考「誤読される『ファウスト』、変奏される青春:二〇〇〇年代中国のライトノベル文芸運動と私の批評的起点」が掲載されている。
郭敬明と『ファウスト』が接触を果たした結果、中国大陸では、日本のライトノベルを「文学」として誤読する独自の受容が起こった。本論では、そこからライトノベルと中国青春小説の文法を接続させる文芸運動が発生した歴史を振り返る。そして、その運動の一角を担った象徴的な文芸誌『漫客・小説絵』を中心に、その文芸的・批評的価値を再確認した上で、KADOKAWAが中国大陸市場に進出する前の、トランスナショナルな想像力の場の形成を検証する5。
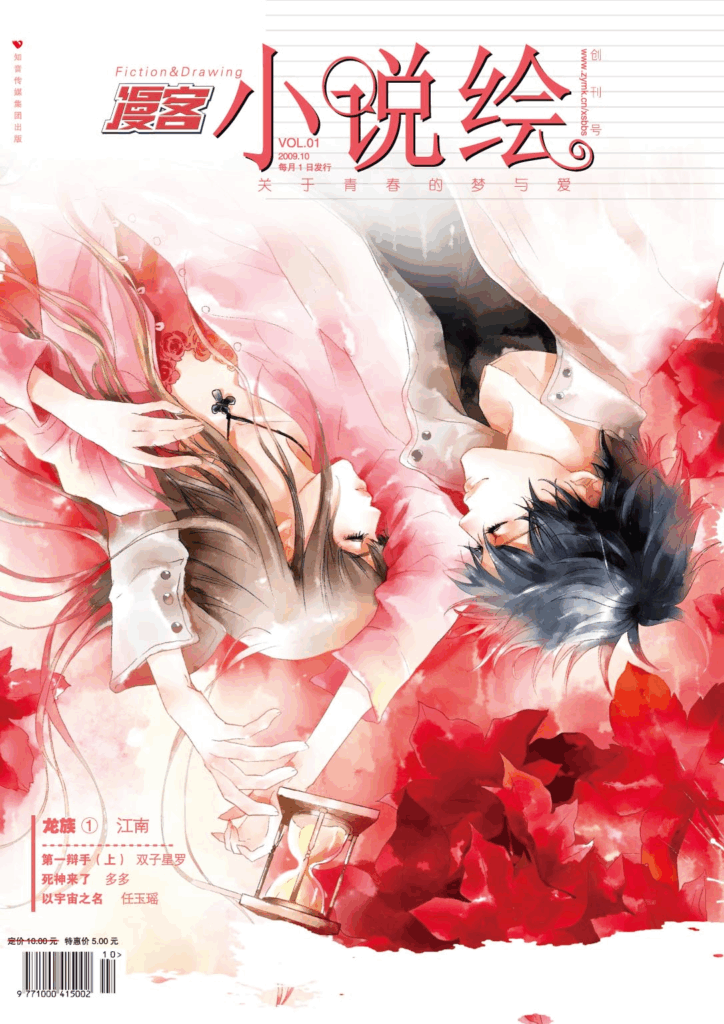
出典:百度百科
次に、甚誰(シェンシェー)による論考「「新概念」と『ファウスト』──二〇〇〇年代中国ライトノベルの可能性について」が続く。彼は中国語文学を専攻しており、私の博士課程での後輩で、かつ郭敬明と同じ上海大学の出身でもある。
この論考は私の文章と相互補完的な関係にあり、中国文芸史という内在的な視点から、郭敬明が果たした役割とその限界、そして「ファウスト的なもの」が中国青年文学に導入された意義を分析する。具体的には、ライトノベルの中国化がいかにして「新概念作文大賽(コンクール)」(入賞者には名門大学への推薦入学権が与えられた)出身の作家たちと接続され、純文学と大衆文芸の境界を揺さぶってきたかを検証している。

出典:「萌芽」ウェブサイト
両論考はいずれも、「ファウスト系」とライトノベルが「中国の文芸制度」という固有の土壌のなかでどのように変奏され、時に模倣を、また時に抵抗を引き起こす起点として機能してきたかを描くものである。「誤読」から始まったこの運動こそが、むしろ中国大陸における「ファウスト系」受容の本質であり、その変奏の軌跡を丁寧に掘り起こす本篇は、本誌の核心をなす論点のひとつを提示している。
2. 香港篇 〜批評と創作の架橋
次に「香港篇」では、繁体字中国語圏における「ファウスト系」の受容と変容、そしてその文芸的・批評的インパクトを、香港という特異な文化交差点を舞台に詳述する。
まず、冒業(ボウギョウ)による論考「港台華文ミステリーにおける「ファウスト系」の臨死と復興」がある。冒業は、日本でも人気を博す華文ミステリーの第一線で活躍するミステリー作家であり、創作だけではなく、ミステリーやオタクカルチャーに関する評論の紹介も香港で精力的に行っている。
2000年代に台湾の出版社を経由して導入された「ファウスト系」ミステリーは、当初はあまり理解されなかったにもかかわらず、2010年代以降に日本のオタク・サブカル批評の翻訳とともに再評価されていく。冒業の論考はその再評価の過程を、多数の作家と作品を通じて鮮やかに描き出す。メタ・ミステリーや「後期クイーン的問題」といったジャンル論が、いかに香港・台湾の華文ミステリー作家たちに影響を与え、独自の実験的作品群を生んだかを明らかにする本論は、東アジアの批評的想像力の変容を示す重要な記録となっている。
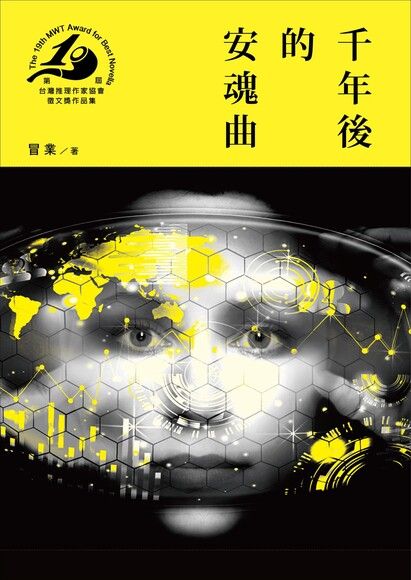
出典:Readmoo読墨電子書
続けて紹介するのは、張彧暋(チョウイクマン)の「日本のサブカルチャー、アニメ・マンガ批評の香港における展開」である。張彧暋は大学教員を務める傍ら、日本のオタク・サブカル批評シーンと密接な関係にあり、批評家・宇野常寛との付き合いも長い。日本の批評番組への出演や、日本での著作の出版など、華文世界と日本の批評界を接続する重要な存在である。
彼の論考は、かつて香港中文大学にて開講した「日本社会とアニメ・マンガ」講座を中心に、日本のゼロ年代批評(大塚英志、東浩紀、宇野常寛ら)を香港の教育実践・同人活動へと導入したプロセスを回顧的に論じる。ここでは『ファウスト』に象徴されるサブカルチャーの知と批評が、いかにして「制度」ではなく「場」として流通し得たかが考察され、アニメ・マンガについて「考える」文化が、香港の学術界や社会運動とも交差しながら生成していく様相が描かれる。

出典:同人評論誌Platform(プラットホーム)Facebook
両論考に共通するのは、『ファウスト』をひとつの起点としつつもそれをローカルな文脈に接続し、新たな創作と批評の回路を開いた実践者たちの営みを、当事者自身の視点から丁寧に記述している点である。香港という場において「ファウスト系」は単なる輸入文化ではなく、批評と創作を架橋する方法論として機能してきた。その軌跡を記録した本篇は、本誌のなかでも特に実践と理論が結びついたユニークなパートである。
3. 台湾篇 〜検閲による想像力の萌芽
台湾篇では、植民地経験・検閲制度・サブカルチャー実践が交差する場に焦点を当て、アニメ・マンガ文化の受容と変容を複層的に描き出す。
まず梁世佑(リョウセイユウ)による論考「変動するパラダイムシフト 台湾、中国大陸、日本におけるアニメ文化の伝播と変容の決定的瞬間」がある。梁世佑は日本のオタクコンテンツの産業研究、輸入業務などのコンサルタントを行う会社を経営しており、近年では日本のオタクカルチャーをテーマにした懸賞論文を主催するなど、華文世界におけるオタクカルチャー研究体制の構築に力を入れている。編集長である私もこの懸賞論文に参加したことがある。
彼の論考は、1990年代の台湾のアニメ雑誌『先鋒動畫』『神奇地帶』を起点に、台湾が日本と華文世界の間に位置する文化的中継地として果たした歴史的役割を検証する。そこでは、日本アニメに対する熱狂的な受容とともに、それを自らの言葉と観点で「研究」しようとする批評文化が誕生し、やがて「ACG」という言葉の誕生とその制度化へとつながっていく過程が描かれる。台湾は、検閲・規制と著作権の狭間で「コピー」を通じてオリジナリティを育てるという、いわば「違法と創造の境界領域」で文化を育んできた。

出典:台湾漫画基地
梁世佑の論考を補完するのが、ntによる回想的論考「一九七〇年代から一九八七年までの台湾における日本マンガを振り返る」である。ntは、前述の「ACG」という言葉を作り上げ、のちに台湾におけるアニメ・マンガ文化の伝播の一角を担う団体「傻呼嚕(シャッフル)同盟」の一員で、オタクカルチャーが華文世界に根づく最初の瞬間を目撃した人物である。また「傻呼嚕同盟」は、東浩紀『動物化するポストモダン』(2001)の繁体字中国語版の監修を手がけており、私自身も彼らが監修する書物を通してゼロ年代批評に接触した。
彼女の論考では、台湾の戒厳令体制下における日本マンガの改変、すなわち描き直し・性転換・思想の書き換えといった検閲操作が、読者の想像力をいかに揺さぶり、「真実」に到達し得ない物語の裂け目を生み出したのかが描かれる。ntは、台湾の読者たちが断片的な知識や図像を駆使しながら「これはもともと日本のマンガなのだ」と直観し、むしろその断絶や抹消の痕跡のただなかに、独自の情動的読解を育てていったことを証言する。それはまさに、検閲制度によって「欠落した情報」と「禁止された原作」への欲望、すなわち本誌が扱う「断絶の欲望」がオタク的想像力を萌芽させた好例である。

出典:誠品線上
この2つの論考は、台湾におけるアニメ・マンガ文化の受容が、メディアによる伝播といった単純なモデルでは見いだせない、検閲や制度とのせめぎあいのなかで育まれたという事実を浮かび上がらせる。そしてその過程こそが、華文世界における特異な「翻訳地」としての台湾の文化的位置を確立する礎となった。
かくして本誌に収められた6本の論考は、それぞれ異なる時代・場所・制度の裂け目から、「ファウスト的なもの=トランスナショナルなもの」としてオタクカルチャーに遭遇した読者たちの実践を記録している。そこにあるのは、単なる輸入や翻訳の歴史ではない。言葉が削られ、図像が塗り潰され、名前が書き換えられた痕跡のなかにこそ、ある種のオタク的感性が目覚め、形を与えられる契機があったのだ。情報の不在が、かえって過剰なほどの想像力を呼び起こし、触れられぬ原作や語られざる文脈への憧憬が、いつしか「断絶の欲望」として文化の底を流れはじめる。
オタクカルチャーの「異邦人」として
私たちがこの同人誌を編んだのは、ある問いに突き動かされてのことだった。なぜあのとき、あの場所で、「ファウスト的なもの」があれほど強く私たちを惹きつけたのか。そしてなぜ、その記憶はいまなお胸の奥で疼き続けるのか。
『ファウスト』という媒体は、単なる日本の文芸誌ではなかった。それは、制度と抵抗の間に揺らめく創作と批評の断片たちが、異なる地域や体制を横断し、インターネットすら超えて呼応し合い、「読む者」から「書く者」への跳躍を促す磁場であった。そこでは、作品はただ享受されるものではなく、自らを変容させ、周囲を変えうる言葉として、読者のなかに息づいていた。
このトランスナショナルな磁場で育った私たちは、『ブルーアーカイブ』のシナリオディレクターisakusanの言葉を借りるならば、「オタクカルチャーの異邦人」6と言ってよいのかもしれない。私たち東アジアのオタクは、日本的なテーマに深く憧れながらも、それを「外部」から観察し、ズレを抱えながら受容してきた者たちである。
だが、それは決して劣位や傍観を意味するものではない。むしろ「異邦人」であるがゆえに獲得しえたメタレベルのまなざしと、複数の文化にまたがる想像力にこそ、オタクカルチャーの新しい地図を描き出す可能性が宿っているのだ。
本誌『東アジアのなかでの「ファウスト系」』に収められた中国大陸・香港・台湾の諸実践は、それぞれ異なる制度・歴史・メディア環境のなかで「ファウスト的なもの」がいかに誤読され、変奏され、回収されながら、なおも生き残ってきたかを証言している。そこには「グローバル化」や「クールジャパン戦略」、あるいは「ローカルな抵抗」といった既存の物語では捉えきれない、もっと複雑で、もっと切実な回路があった。検閲によって塗り潰されたマンガのひとコマ、時代を先取りしすぎた小説ジャンル、正史に回収されていった青春文学の軌跡──それらすべてが、私たちの「オタク」としての身体にトランスナショナルな痕跡を刻んでいる。
だからこそ、私たちは「異邦人」として語らなければならない。作品の内側からだけでなく、その外部から、ズレから、制約のなかから。トランスナショナリティとは、単なる距離を隔てた移動ではない。そうではなくて、不可視の抑圧や誤配や断絶を引き受けながら、なおも他者と連なろうとする感情の軌跡なのである。
『ファウスト』はまさに、その軌跡が描き出される震源地だった。それはKADOKAWA的な物語や制度とは違う形で、誤読として、あるいは破片として、東アジア各地の想像力を繫ぎ続けていた。そこに生まれたズレや混淆、再解釈の余地こそが、オタクカルチャーのトランスナショナルな創造性の源だったのだ。
本誌は、そうした声を掘り起こすためにある。
もし、読者のあなたが、この同人誌を手に取ることで、自らの地図の断片を思い出したのであれば、ぜひ私たちと一緒に声を上げ、自分自身の「トランスナショナリティ」を記述してほしい。そのときは、本誌のタイトルである『東アジアのなかでの「ファウスト系」』を使っても構わない。そして願わくは、本誌が少しでもあなたの語りの力にならんことを。
著者

紅茶泡海苔 Kocha-awa-nori
立命館大学大学院先端総合学術研究科博士課程修了。博士(学術)。専門はアニメーション史および表象文化論。日本の文芸批評史を翻訳・紹介する中国の批評団体「屋頂現視研」初期メンバー。オタクカルチャーおよびその背後にある文芸批評を中心に批評活動を展開している。ペンネーム「紅茶泡海苔」および本名「王琼海」名義で『ユリイカ』『情況』『ferne』など日本の雑誌・同人誌に批評を多数寄稿。「2020年代の批評ライン」を主宰し、青春ヘラ・感傷マゾ・低志会を繫いた闇のフィクサー。
\ ご支援よろしくお願いします! /
関連商品

東アジアのなかでの「ファウスト系」
華文世界とオタクカルチャーのトランスナショナルティ
KADOKAWAの「正史」への抵抗、オタクカルチャーの異邦人、中韓オタクコンテンツの背後に潜む「ファウスト的なもの」──。華文世界を起点に、文芸誌『ファウスト』が東アジアの文化実践で果たした役割を紐解く。
紅茶泡海苔/甚誰/冒業/張彧暋/梁世佑/nt
2025年5月11日発行
詳しい紹介はこちら!
関連記事




脚註
- 『ブルーアーカイブ オフィシャルアートワークス』、 一迅社、2022年、285–286頁。 ↩︎
- 「【特別対談】『Fate』奈須きのこ ×『崩壊:スターレイル』David Jiang ―「本当に自分が描きたいものかどうかわからない」に、どうやって立ち向かう? 「夢」と「欲望」を具現化する方法」、電ファミニコゲーマー、2024年3月22日。 ↩︎
- 2000年代以降は、ライトノベルの流行とともに、小説(Novel)を加えて「ACGN」と称することもある。 ↩︎
- 例えば、この言葉における「Game」の意味合いは日本と若干のズレがある。日本においてオタクカルチャーにおける「ゲーム」と言えば、まずパソコンでプレイされる「美少女ゲーム」がその中心にあり、そこから派生した現代のアニメ・マンガ調のスマホゲーム、そしてアニメ風のデザインを取り入れたJRPGなどのコンソールゲームが想起されるであろう。だが、華文世界では欧米風デザインの日本のコンソールゲームも「G」に含めている。『バイオハザード』や『メタルギアソリッド』シリーズなどのゲームがアニメ・マンガと同じく、オタクカルチャーというカテゴリーに入るかと言うと、入りそうで入らない微妙なところにあるが、「ACG」ではアニメ・マンガと同列に扱われるのが普通である。 ↩︎
- この論考は、私がかつて北出栞編『ferne』(2021)に寄稿した「不可能性としてのセカイ系──杉井光の忘却の否定神学について」、そして大阪大学感傷マゾ研究会・早稲田大学負けヒロイン研究会合同誌『負傷』(2022)所収の「青くてエモい小説たち──「ブルーライト文芸」座談会」で話した内容、多摩地区表象文化論・动画批評研究会(2021年10月23日開催)での発表「中国における「ゼロ年代」の受容──ライトノベル文化からゼロ年代批評へ」に通ずる内容でもある。興味のある人は、これらの文章・発表も参照してほしい。 ↩︎
- 「日本初『ブルーアーカイブ』独占インタビュー:キャラクターは人間であり、作家は組織であり、虚構は真実であること」、電ファミニコゲーマー、2024年6月28日。 ↩︎


